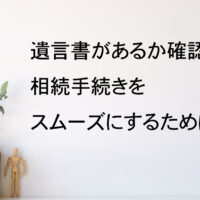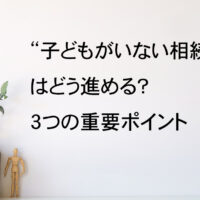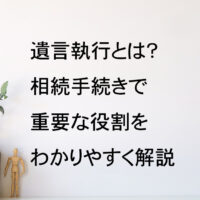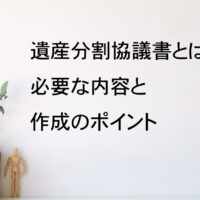コラム
2.122025
宇都宮の相続手続き解説シリーズ 第2回|相続関係説明図・法定相続情報一覧図とは?使い分けと作り方
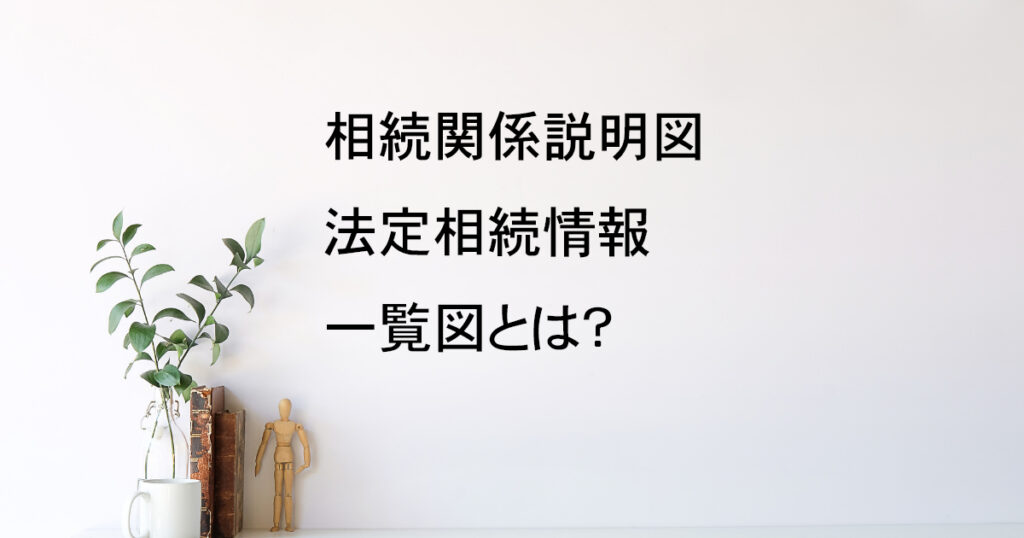
宇都宮の相続手続き解説シリーズ 第2回
相続関係説明図・法定相続情報一覧図とは?使い分けと作り方
栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。このシリーズでは、相続に関するさまざまな手続きを、一つずつ丁寧に解説しています。
第2回のテーマは「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」という名前の似た2つの書類についてです。どちらもお亡くなりになった方(被相続人)とそのご家族など(相続人)とのつながりを整理した図です。ただ、あまり触れる機会がなければ、違いがわかりにくいですよね。実際に「これって両方必要なの?」「どうやって作るの?」といったご相談をよくいただきます。
今回は、それぞれの特徴や違い、使い方、作り方をわかりやすくご紹介いたします。
目次
「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の違いとは?
―亡くなった方が図に「載る」か「載らない」かが、実は大きな分かれ道―
相続の手続きにおいてよく耳にする「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」。この二つ似ているようで実は大きな違いがあります。
その違いの一つが「すでに亡くなっいる相続人が図の中に記載されるかどうか」です。
相続関係説明図とは?
「相続関係説明図」は、被相続人(亡くなった方)と相続人とのつながりを図で表したものです。
・亡くなった方(被相続人)
・その配偶者や子ども、兄弟姉妹などの相続人
全員記載され、すでに亡くなっている方の情報も載るのが特徴です。つまり、「誰が亡くなり、誰が相続人なのか」が視覚的に分かる図となります。
法定相続情報一覧図とは?
一方、「法定相続情報一覧図」は、法務局に提出して発行してもらう公的な証明書類です。これは、相続人が複数の金融機関や行政機関に同じ戸籍一式を何度も提出しなくて済むように、法務局が戸籍を確認して、相続関係を公的に証明してくれる制度です。
✔ 図の中に「既に亡くなっている相続人」は載らない
図として記載されるのは「相続人のみ」です。つまり、「誰が法定相続人であるか」を証明するための図なのです。
相続手続きにおける「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の役割とは?
相続が発生したとき、銀行・法務局・証券会社などで手続きを進める際には、「相続人が誰で、どのような関係性か」を明示する必要があります。
その際に活用されるのが、これらの書類です。
| 書類名 | 特徴 |
|---|---|
| 相続関係説明図 | 亡くなった方を含めた家族関係を図示する(銀行・法務局など) |
| 法定相続情報一覧図 | 法務局が交付・公的証明として提出でき、戸籍の束を繰り返し提出する手間が省ける(複数の金融機関・法務局など) |
「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の作成方法
相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図とは、戸籍に記載された情報をもとに、被相続人と相続人の関係を家系図のような形で図解したものです。主に不動産登記や少数の銀行口座の解約、証券の名義変更などの場面で、「相続人がこの人たちで間違いありません」という証明として提出されます。
この図は法的に決まった形式がないため、手書きでもパソコン作成でも構いません。
ただし、次のような内容を正確に記載する必要があります
・被相続人の氏名・生年月日・死亡日
・相続人の氏名・続柄・生年月日(死亡している人も記載)
・配偶者や代襲相続人なども含めた全体構成
法定相続情報一覧図の作成方法
法務局が認証する「相続人一覧の公的証明」
法定相続情報一覧図は、戸籍一式と作成した法定相続情報一覧図をもとに、法務局が“公的な証明書”として交付する書類です。この一覧図があれば、複数の機関で繰り返し戸籍を提出する必要がなくなり、相続手続きを効率よく進めることができます。
取得の流れ
1.被相続人の戸籍類と法定相続情報一覧図を作成して準備(法務局のHPにテンプレートがあります。)
2.法務局へ「一覧図の交付申出書」を提出
3.後日、法定相続情報一覧図が交付される(複数枚の交付も可能です。)
🔗 相続人が誰か、どう調べるのか知りたい方はこちらを先にご覧ください
👉 第1回|相続人の調べ方|戸籍収集の基本と注意点
当事務所では、これらの違いや役割をご説明しながら、ご相談内容に応じて、どちらを作成すべきかもご提案しています。また「どちらを作ればいいの?」「自分で作るのは不安…」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。戸籍の収集から相続関係説明図・法定相続情報一覧図を作成から交付受取まで対応しております。
よくある注意点と実務のコツ
❗ 相続関係説明図のミスは手続きに影響
・記載内容が戸籍と一致していない
・死亡している相続人が抜けている
・続柄の記載が曖昧 など
自分で作成してみたのはいいけれど…万が一相続人に抜けや漏れがある場合は、相続手続きがストップしてしまうこともあります。
❗ 法定相続情報一覧図は「申出人」にも注意
・申出できるのは「法定相続人本人」か「その代理人(専門家)」のみ
・委任状や本人確認資料の提出が必要
提出の際に、書類の不備や記載漏れ・誤字などがある場合には、数回法務局に足を運ぶこととなってしまいます。
Kanade行政書士事務所ができること

相続手続きの基本サポート
・相続人調査(戸籍収集・特定)
・財産目録(遺産目録)の作成
・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
・遺産分割協議書の内容・案分作成
金融機関・証券会社などへの手続きサポート
・証券会社向けの相続手続き書類作成
・必要書類・名義変更等サポート
安心できるサポート体制
・初回相談無料
・宇都宮市を中心に、柔軟かつスピーディーな対応
・必要に応じて、司法書士・税理士との連携によるワンストップ支援も可能です。
まとめ|「図にする」ことで相続がスムーズに進みます
戸籍を見てもよくわからない…という方は多いものです。特に昔の戸籍は読み解くのが難しい場合も多いです。ですが、相続手続きには相続関係説明図や法定相続情報一覧図が必要です。ご自分での作成に心配な場合は、お気軽にご相談ください。
次回予告|第3回はこちら!
👉 相続手続きが初めての方は、10回シリーズでわかりやすく解説した
[相続手続き解説シリーズまとめページ]をご覧ください。