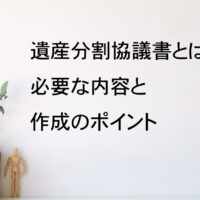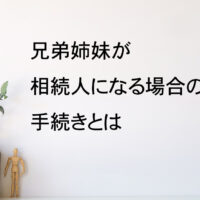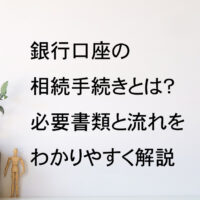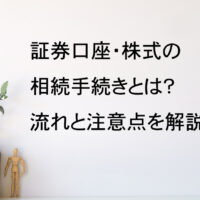コラム
2.112025
宇都宮の相続手続き解説シリーズ 第1回|相続人の調べ方|戸籍収集の基本と注意点
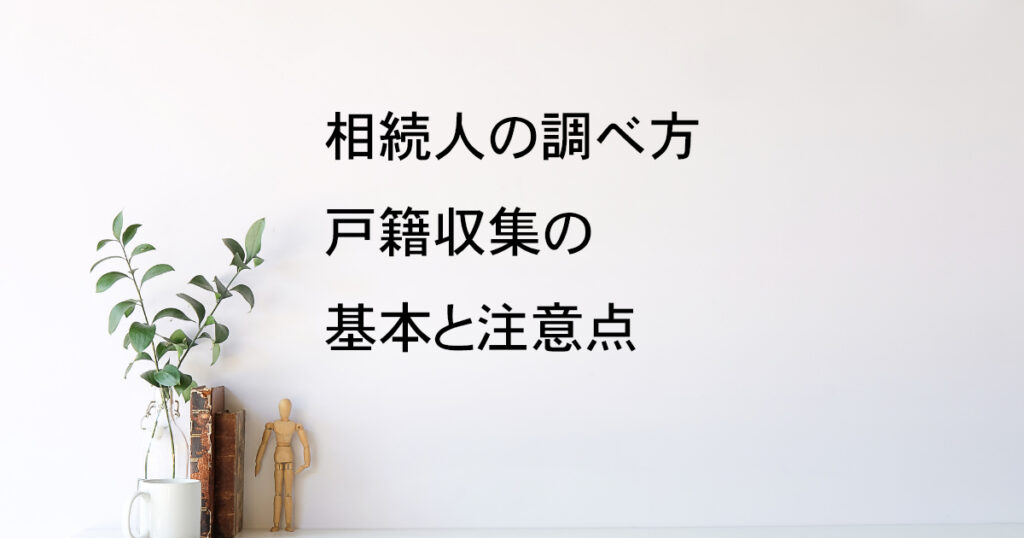
宇都宮の相続手続き解説シリーズ 第1回
相続人の調べ方|戸籍収集の基本と注意点
栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。このブログでは、相続の基本的な手続きについて、一つずつ丁寧に解説してまいります。
第1回のテーマは、相続の出発点ともいえる「相続人の調べ方」です。「誰が相続人なのか、正確にはわからない…」「戸籍ってどこまで集めればいいの?」そういった不安を感じている方は少なくありません。このような方に向けて、戸籍の読み方や収集のコツ、実務での注意点をわかりやすくご紹介します。
目次
相続人を調べることから始まります
相続の手続きで最初にすべきことは、「誰が相続人かを正確に把握すること」です。この調査が曖昧なままでは、どの手続きも進めることができません。相続人を正確に確定するためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍を遡って収集する必要があります。これを一般的に「戸籍の収集」「相続人調査」と呼びます。
戸籍でたどる相続人の確認方法とは?
ステップ1|「死亡の記載がある戸籍」を確認
まずは市区町村役場で、被相続人の最新の戸籍(除籍)を取得します。そこには「〇年〇月死亡」という記載があります。この情報を起点に、過去にさかのぼって戸籍を集めていきます。
ステップ2|出生から死亡までの連続した戸籍を集める
相続人調査では、出生から死亡までの「戸籍のつながり」がすべて必要です。転籍・結婚・離婚などのタイミングで戸籍が変わっていることが多く、1人につき3〜5通以上の戸籍を取り寄せることもよくあります。
新制度のご紹介|戸籍の広域交付制度とは?
相続に必要な戸籍の収集が、これまでよりも便利になったことをご存じでしょうか?2024年3月1日より「戸籍の広域交付制度」が施行され、一つの役所で出生から死亡までの戸籍をまとめて取得できるようになりました。これまでは戸籍は「本籍地の市区町村役場」でしか取得できませんでしたが、この制度により、住んでいる場所や勤務先の最寄りの役所で、被相続人の戸籍を取得できるようになりました。
主な特徴
・本籍地が遠方でも、現在地近くの役所で取得できる
・複数の本籍がある場合も、1か所でまとめて請求可能
・利用できるのは「本人・配偶者・直系尊属・直系卑属」のみに限定
・郵送請求・代理人の利用はできず、本人が窓口に出向く必要ありこの制度によって、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を一括で集めることが可能になり、特に高齢の方や遠方の親族にとっては、手続きの大きな負担軽減となります。
🔗 相続人を“図”にまとめたい方はこちらも参考にどうぞ
👉 第2回|相続関係説明図・法定相続情報一覧図とは?使い分けと作り方
よくある注意点と実務のひと工夫
戸籍が分かれていると、相続手続きが止まる?
ー転籍や婚姻による「戸籍のつながり切れ」にご注意をー
相続手続きで避けて通れないのが、「戸籍の収集」です。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をたどることで、法定相続人を正確に確認することができます。ところが、この戸籍集め、意外とスムーズにいかないケースが多いのです。
戸籍は「引っ越し」や「結婚」で分断される
戸籍は、本籍地の移動(転籍)や婚姻による戸籍の編成によって、新たに作り直される仕組みです。そのため、たとえ一人の人生であっても、複数の市区町村にまたがって戸籍が存在することは珍しくありません。
たとえば…
・結婚して、夫の本籍地へ転籍した
・引っ越しに合わせて本籍も変更した
・一度離婚して旧姓に戻ったあと、再婚した
といった人生の節目で、そのたびに「新しい戸籍」が編成されている可能性があります。
「つながりが切れている」戸籍とは?
相続人調査では、出生から死亡まで戸籍が一つの流れで確認できることが前提です。ところが、
・転籍の履歴が漏れていた
・婚姻・離婚歴が抜けていた
・古い戸籍がすでに廃棄・改製されている
といった理由で、戸籍の連続性が途切れてしまう(つながりが切れる)ことがあります。このような状態になると、戸籍の調査がストップしてしまい、相続人の確定ができない=手続きが前に進まなくなってしまいます。
解決には「経験と地道な調査」が必要
こうしたケースでは、戸籍の読み解き方や古い戸籍の取得ルートを熟知している専門家に依頼するのが安心です。行政書士などの相続手続きの実務に慣れた専門家であれば、
・改製原戸籍・除籍謄本の請求先を正確に判断
・推定される転籍先から戸籍をたどる
・時代ごとの表記ルール(旧漢字や略字)を読み解く
といった、手間のかかる調査もスムーズに対応できます。
戸籍がつながっていないと、相続は進みません相続。相続て手続きには、「誰が相続人か」を戸籍で証明するところからスタートします。戸籍がバラバラになっていたり、取得先が分からなくなっていると、思いがけず時間も費用もかかってしまうことがあります。
Kanade行政書士事務所では、複雑な戸籍調査やつながりが切れているケースにも対応しています。
宇都宮市や近隣市町の戸籍調査に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
戸籍をたどると「知らない相続人」が見つかることも
ー相続では、思わぬ事実が戸籍に記されていることがありますー
相続手続きでは、まず「誰が相続人なのか」を確定させることから始まります。そのために必要なのが、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍です。戸籍をたどる過程で、次のようなケースが見つかることがあります。
実際にあったケースの一例
・「前の結婚で子どもがいたことを、家族は誰も知らなかった」
・「成人したあとに認知した子がいた」
・「昔、養子縁組をした」
これらはすべて、戸籍にきちんと記録されています。つまり、遺族が知らなくても、法律上は相続人としての権利があるのです。
読み解きにはコツがいる
古い戸籍は手書きだったり、旧漢字や略字が使われていたりして、読み慣れていないと内容を理解するのが難しいこともあります。また、以下のような記載を読み取れるかが、相続人確定のカギになります。
・「認知」や「養子縁組」の記録
・婚姻・離婚の履歴
・出生の事実や転籍の流れ
これらを一つひとつ丁寧に確認していくことが、正確な相続人の把握につながります。
戸籍には、想像以上に多くの情報が詰まっています
相続手続きをスムーズに進めるためには、戸籍の収集と読み解きがとても重要です。家族の記憶だけでは分からない情報も、戸籍にはしっかり記載されているためです。
知らなかった相続人が後から見つかると、協議のやり直しやトラブルに発展してしまうこともあります。だからこそ、相続手続きの最初の段階で「戸籍収集」や「相続人調査」をしっかり行うとが必要があります。
戸籍収集から相続関係説明図・法定相続情報一覧図へ
「戸籍を取り寄せたけど、内容がよく分からない」そんなご相談をよくいただきます。
戸籍は相続手続きに必要不可欠ですが、昔の筆記体や略字、転籍・婚姻などの記載が複雑で、読み解くのは簡単ではありません。そこで当事務所では、戸籍の内容をもとに「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」を作成しています。
これは、相続人同士の関係を図にまとめたもので、
✔ 相続人が誰かをひと目で確認できる
✔ 登記や金融機関の手続きにそのまま使える
✔ 相続漏れや手続きミスを防げる
といったメリットがあります。
当事務所では、戸籍の収集から「相続関係説明図」・「法定相続情報一覧図」作成まで一貫サポート。「自分で確認するのは不安」「何が必要かわからない」という方も、安心してご相談ください。
Kanade行政書士事務所がサポートできること

相続手続きの基本サポート
・相続人調査(戸籍収集・特定)
・財産目録(遺産目録)の作成
・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
・遺産分割協議書の内容・案分作成
金融機関・証券会社などへの手続きサポート
・証券会社向けの相続手続き書類作成
・必要書類・名義変更等サポート
安心できるサポート体制
・初回相談無料
・宇都宮市を中心に、柔軟かつスピーディーな対応
・必要に応じて、司法書士・税理士との連携によるワンストップ支援も可能です。
「戸籍収集って面倒くさそう…」「どこまでが相続人か曖昧で不安」そんな方は、最初の一歩からお任せください。
まとめ|まずは相続人の把握が安心の第一歩です
相続人の調査は、すべての相続手続きの土台となるものです。この部分が正確でなければ、遺産分割協議も銀行手続きも不動産の名義変更も進められません。戸籍は慣れていないと難しく感じるかもしれませんが、一つずつ手順を踏めば、確実に整理できます。
Kanade(かなで)行政書士事務所では、相続のはじめの一歩から、ていねいにサポートしています。どうぞお気軽にご相談ください(初回無料です)。
次回予告|第2回はこちら!
👉 相続手続きが初めての方は、10回シリーズでわかりやすく解説した
[相続手続き解説シリーズまとめページ]をご覧ください。