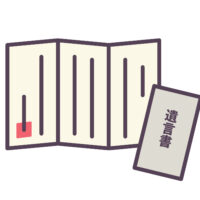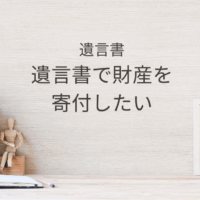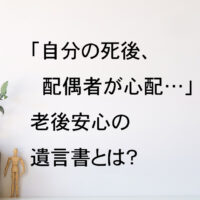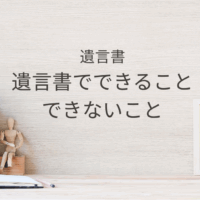コラム
5.152025
未成年の相続人がいる場合の遺言書|特別代理人と財産管理の工夫
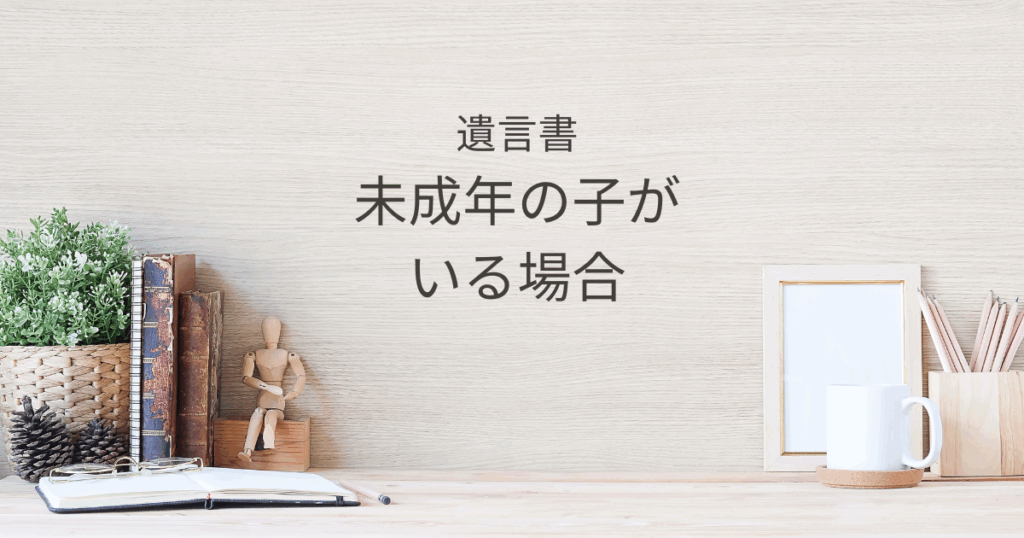
目次
未成年の相続人がいる場合の遺言書|特別代理人と財産管理の工夫
家族の中に未成年のお子さまがいる場合、遺言書は一層大切な意味を持ちます。
「まだ小さい子に相続が発生したらどうなるの?」
「財産の管理は誰がするの?」
「他の相続人とのトラブルを防ぐには?」
こうした不安は多くの親御さんが抱えるものです。
この記事では、未成年の相続人がいる場合の遺言書の書き方や、特別代理人・財産管理の工夫について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
未成年の相続人とは?法律上の立場を確認
まず、未成年でも相続権は大人と同じく法律で保障されています。
被相続人が亡くなった瞬間に「法定相続人」としての権利が発生し、遺産分割の対象となります。
ただし、未成年者は法律行為を単独で行うことができません。
相続手続きには「法定代理人(親権者)」が必要になります。
法定代理人と遺産分割
通常、親が未成年の子の代理人となり手続きを進めます。
しかし、その親自身も相続人である場合、利害が対立するため「特別代理人」を選任する必要があります。
この仕組みを知らずに進めると、分割協議が無効になるリスクがあります。
遺言書がない場合に起きる問題
遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
未成年の子がいる場合、特別代理人の選任が必須となり、手続きが煩雑化します。
例:
-
父が亡くなり、母と未成年の子2人が相続人
-
母が子の代理人になれず、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要がある
-
選任に数か月かかる場合もある
遺言書があれば、こうした手続きを回避し、スムーズに相続を進められます。
遺言書でできる配慮と工夫
未成年の子のために、遺言書で以下の配慮を行うことが可能です。
1. 遺産分割方法を指定する
「自宅を長男に遺贈し、預貯金を均等に分ける」といった具体的な分配を明記すると、遺産分割協議が不要になり、特別代理人の選任も回避できます。
2. 財産管理の方法を工夫する
「成年に達するまで預貯金の管理は〇〇に任せる」など、信託や管理方法を指定することで、無用な浪費や混乱を防げます。
3. 付言事項で想いを伝える
「あなたが成人するまで、この財産が生活を支えることを願っています」といった言葉を残すことで、家族の理解が深まります。
特別代理人とは?選任の流れ
特別代理人の役割
特別代理人は、未成年の相続人の利益を守る立場で遺産分割協議を行います。
親族や弁護士などが選ばれることが多いです。
選任までの流れ
-
家庭裁判所へ申立て
-
選任審査(約1〜2か月)
-
特別代理人決定
-
遺産分割協議の実施
遺言書があれば、そもそも遺産分割協議が不要になるため、この流れを省略できます。
よくある質問(Q&A)
Q. 未成年の子だけに多く遺すことは可能ですか?
A. はい、可能です。ただし、他の相続人の遺留分に配慮する必要があります。
Q. 特別代理人は誰がなるのが良い?
A. 家族内に適任がいない場合、弁護士や司法書士が選任されることが多いです。
Q. 何歳まで特別代理人が必要?
A. 子が成人(18歳)になるまで必要です。
公正証書遺言で確実な準備を
未成年の相続人がいる場合、遺言書の不備や紛失は大きなトラブルを招きます。
公正証書遺言は以下のメリットがあります。
-
法的効力が確実
-
内容の不備を防げる
-
公証役場に保管される
Kanade行政書士事務所では、ヒアリングから作成まで丁寧にサポートします。
まとめ|子どもの将来を守る遺言書
小さなお子さまがいる場合、親として「万一の備え」は欠かせません。
遺言書は財産だけでなく、安心や支援を残すための大切な手段です。
不安を先送りせず、できるだけ早めの準備を心がけましょう。
▶ ご相談ください
Kanade行政書士事務所では、未成年の相続人がいるご家庭の遺言書作成を多数お手伝いしています。
ご家族が安心できる将来を、一緒に考えましょう。