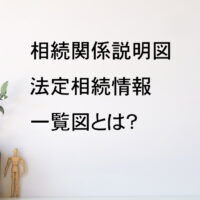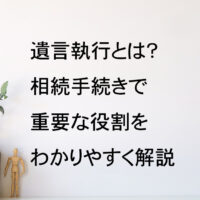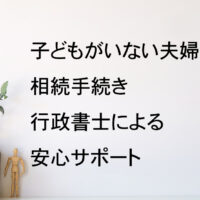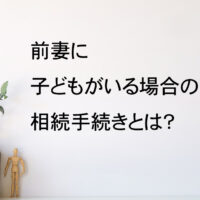コラム
2.72025
再婚相続シリーズ 第2回|現配偶者と前妻の子が相続人に?宇都宮の相続手続きで注意すべきこと
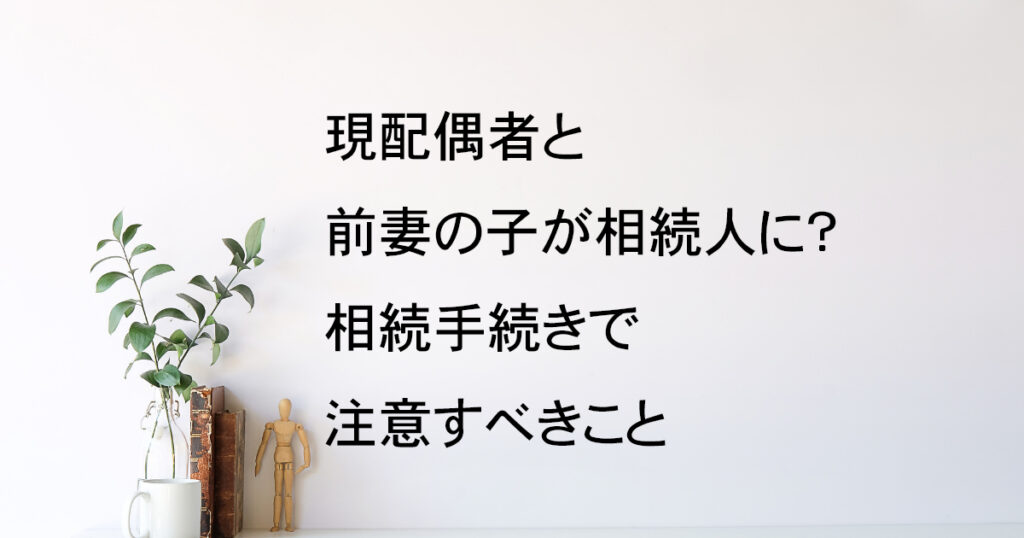
「再婚と相続」全5回シリーズ|第2回
栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。今回のテーマは、「現配偶者と前妻の子が相続人になる場合の注意点」についてです。
再婚家庭の場合「今の家族」で生活をしていても、いざ相続の場面になると「前の家族」が関わってくることがあります。こうした場合、実際の相続が必要になると、戸惑いを感じる方も少なくありません。
特に、「亡くなった夫の遺産を、前妻との子どもと分けることになるなんて…」というケースでは、感情面の摩擦も起きやすく手続きは慎重に進める必要があります。
前妻に子どもがいる相続の基本構造は
第1回|前妻に子どもがいる場合の相続手続きとは?
目次
配偶者と前妻の子、なぜ両方が相続人になるの?
法定相続では亡くなった方に子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人になります。たとえ再婚していて疎遠であったとしても、前妻との子どもも法定相続人です。
例:配偶者+前妻の子が1人の場合
・配偶者:1/2
・前妻の子:1/2
相続分はどうなる?具体的なシミュレーション
夫が亡くなり、前妻との子が2人、現配偶者がいるケース
・配偶者:1/2(実子なし)
・子2人(前妻との子):1/4ずつ
たとえば、夫の遺産総額が6,000万円あったとします。
・不動産(自宅):4,000万円
・預貯金:2,000万円
この場合の法定割合は以下のようになります。
| 相続人 | 法定割合 |
|---|---|
| 現在の配偶者 | 3,000万円 |
| 前妻との子① | 1,500万円 |
| 前妻との子② | 1,500万円 |
◯配偶者が「自宅を相続」したい場合
問題はここからです。配偶者が自宅(4,000万円)を相続しようとすると…
・法定割合通りの場合、配偶者は3,000万円なので、1,000万円分は超過
・この差額を現金で他の相続人(前妻との子2人)に渡すか
・前妻の子ども2人の同意を得て、自宅の「名義変更」をする必要があります
つまり、家や預金の名義変更にも、前妻の子どもを含む全員の同意が必要になるのです。このように、前妻との子どもも法的に「相続人」である以上、現配偶者だけで相続の手続きを進めることはできません。
実際には…
・書類のやり取りがスムーズにいかない
・連絡が取れない、もしくは関係性が悪い
・遺産分割協議で揉める など
相続手続きがなかなか進められないといった場合も多いでしょう。
※本記事のシミュレーションは、相続税や基礎控除などの税務上の要素は考慮せず、わかりやすさを重視して法定相続分の概要を解説しています。実際の手続きには専門家への相談をおすすめします。
宇都宮でのご相談事例
ケース①|「気まずさがずっと心に残ってしまって…」
ご相談者:60代女性・宇都宮市在住
夫には前妻との間に娘さんがいて、昔から「とてもいい子だよ」と話は聞いていました。
実際、年賀状のやり取りもしていましたし、疎遠だったわけではありません。
でも、夫が亡くなって相続の話になったときに「財産の半分は私がいただきます」とハッキリ言われて、なぜかすごく気まずくなってしまって…。
これからどう向き合えばいいか、悩んでいます。
表面的には関係が悪くなくても、“相続”という場面になると距離感が一気に変わることがあります。
感情と手続きのギャップに戸惑う方は、少なくありません。
ケース②|「会ったこともない相手と遺産を分けるなんて…」
ご相談者:50代女性・宇都宮市在住
夫には前の結婚で息子さんがいるのは知っていましたが、私は一度も会ったことがなくて…。
夫は「もう連絡も取っていない」と言っていたので、まさかその息子さんと遺産を半分に分けることになるなんて思ってもいませんでした。
書類を送るにも「どう切り出せばいいのか…」と悩んでしまい、手続きが止まったままです。
このように、戸籍には載っていても実際には交流がない相続人がいる場合、精神的な負担が非常に大きくなりやすいのです。
話し合いが難しいときの注意点と対策
・相続人全員の同意が必要
→ 不動産や預貯金の手続きは、全員の実印・印鑑証明が求められるケースが多いです。
・相手との連絡がスムーズに取れないことも
→ 感情的にならず、事実ベースでの丁寧な対応が鍵になります。
相続人間の調整で難航した事例は
第4回(子なし相続シリーズ)|兄弟姉妹への相続は複雑?
対策①:遺言書で配偶者をしっかり守る
配偶者に多めの財産を遺したい場合、遺言書が必須です。
「全部任せるよ」と言われていても、書面がなければ法定相続どおりに分けられてしまいます。
・公正証書遺言なら、家庭裁判所の検認不要でスムーズ
・遺留分に注意(前妻の子にも最低限の権利がある)
対策②:現在の配偶者に連れ子がいる場合は、養子縁組で連れ子にも相続権を
実子はいないが、現在の配偶者の連れ子と一緒に生活している場合は、その配偶者のお子さんと法的な親子関係(養子縁組)がなければ相続人にはなりません。
・養子縁組をしておけば、現妻の連れ子にも法定相続権が生まれる
・「現家族に多くの割合を残したい」場合に有効な手段
詳しくはこちらをご覧ください
第3回|連れ子に財産を残す3つの方法
Kanade行政書士事務所ができるサポート内容

当事務所では、再婚家庭の相続について、次のようなご相談に対応しています。
・相続人の調査・戸籍収集
・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
・遺言書(公正証書)の作成支援
・預貯金等の相続手続き支援
・他士業(税理士・司法書士)との連携によるワンストップ対応
最後に|今ある家族を守るための“相続の一歩”を
現配偶者と前妻の子が相続人になる。前婚でお子さんがいる場合の再婚家庭においては、避けて通れない現実です。ですが、遺言や養子縁組など、法的な備えを通じて「今の家族を守る」ことは十分に可能です。
Kanade(かなで)行政書士事務所では、法律の知識だけでなく「今のあなたの思い」を汲み取ったサポートを心がけています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。初回は無料です。
お問い合わせフォーム:こちらから