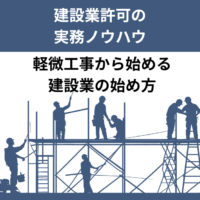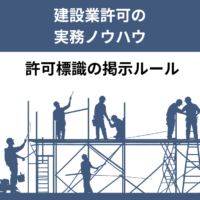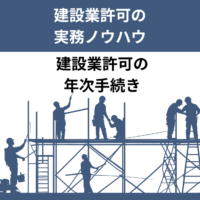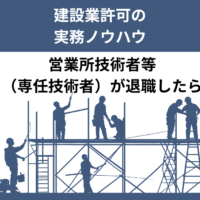- Home
- 建設業許可の実務ノウハウ
- 建設業許可の実務経験証明をわかりやすく|栃木県制度にもとづく書類準備と記載のヒント
コラム
11.42025
建設業許可の実務経験証明をわかりやすく|栃木県制度にもとづく書類準備と記載のヒント

建設業許可を申請するとき、「実務経験証明書」の書き方に悩む方は多いのではないでしょうか。
特に、営業所技術者等(専任技術者)としての経験を証明する場面では、どんな書類が必要なのか・どの期間を証明できるのかがあいまいになりがちです。
この記事では、栃木県の建設業許可制度をもとに、実務経験証明の考え方から書類準備のコツまでを、行政書士としての実務視点でわかりやすく解説します。
目次
実務経験証明とは?まず押さえておきたい基本
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに営業所技術者等(専任技術者)を配置する必要があります。
営業所技術者等(専任技術者)になるには、次のいずれかの要件を満たすことが求められます。
-
国家資格などの資格要件を持っている
-
10年以上(学歴等により短縮あり)の実務経験がある
ここでいう「実務経験」とは、単に建設現場で働いた期間ではなく、許可業種に該当する工事の実務に従事した期間を意味します。
例えば「とび・土工工事業」で申請する場合は、その業種に該当する工事に携わった期間のみがカウント対象です。
栃木県で認められる実務経験の証明書類
栃木県では、経験を裏づけるために複数の証明資料を組み合わせて提出場合もあります。
実際の審査では、次のような書類が多く活用されています。
| 書類の種類 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 工事契約書または注文書・請書 | 契約当事者や工事内容、金額、期間がわかるもの。 |
| 請求書・入金記録など | 工事の実施時期や金額を補完する資料。(あくまでも補完) |
これらの資料を「いつ・どんな工事に関わっていたか」がわかるように整理して添付することが大切です。
一つの工事だけで証明しようとせず、複数年にわたる記録を積み重ねるイメージで準備しましょう。
3.実務経験証明書の書き方と注意点
実務経験証明書は、申請者自身や元勤務先などが作成し、内容を証明する書類です。
記載の際は次のポイントを意識しましょう。
記載のポイント
-
工事名は実際の内容がわかる具体的な表現にする(例:「住宅基礎工事一式」「外構ブロック積み工事」など)
-
工事期間は「〇年〇月~〇年〇月」と明確に記載
-
複数の工事を合算して10年以上になるよう整理
-
元請・下請の別も明記
よくある誤り
-
仕事内容が抽象的すぎて、業種との関連が不明瞭
-
勤務期間と工事期間が一致していない
-
会社名の変更・廃業などにより証明者が不明確
特に「証明者欄」に記載する担当者が実在するかどうかは、審査でも厳しく確認される場合もあるため注意が必要です。
4.実務経験の期間計算と例外ケース
実務経験年数のカウントは、実際に該当業種の工事を行った期間が基準です。
ただし、以下のような例外もあります。
-
学歴(建設関連学科卒業)により、必要年数が短縮される
-
途中で業種が変わった場合、該当部分のみ算入可能
-
自営業者の場合、請負実績と帳簿記録で証明可能
例)
専門学校(土木科)卒業 → 実務経験年数は 7年 に短縮可能
高卒 → 10年 の実務経験が必要
5.申請前に確認したいチェックポイント
申請書を提出する前に、次の点を必ず確認しましょう。
-
記載内容と添付書類の日付・期間が一致しているか
-
業種名の整合性がとれているか
-
証明者の署名・押印があるか
-
書類に修正跡や矛盾がないか
書類の整合性が取れていないと、再提出を求められることがあります。
初回で通るよう、丁寧な準備を心がけましょう。
まとめ ― 「経験を見える化」することで次の一歩へ
建設業許可の実務経験証明は、単なる書類作成ではありません。
これまでの仕事の積み重ねを“形にする”過程でもあります。
経験の整理を通じて、自社の強みや得意分野が見えてくることも少なくありません。
それが今後の事業計画や入札戦略につながるケースもあります。
Kanade行政書士事務所では、栃木県の制度や審査基準に沿った実務経験証明の作成支援・書類チェックを行っています。
「どの工事を証明に使えるのか」「証明者がいない場合はどうするか」など、具体的なケースにも丁寧に対応しています。
一つひとつの実績を大切に、次のステップ――営業所技術者等(専任技術者)としての登録、そして許可取得へとつなげていきましょう。