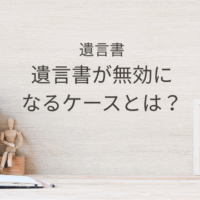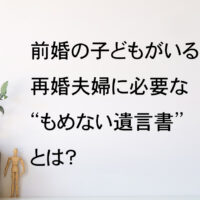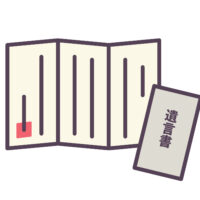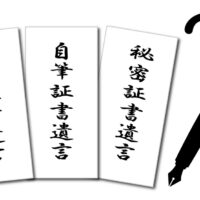コラム
5.212025
遺言執行者とは?誰を選ぶべきかとその役割・責任について丁寧に解説
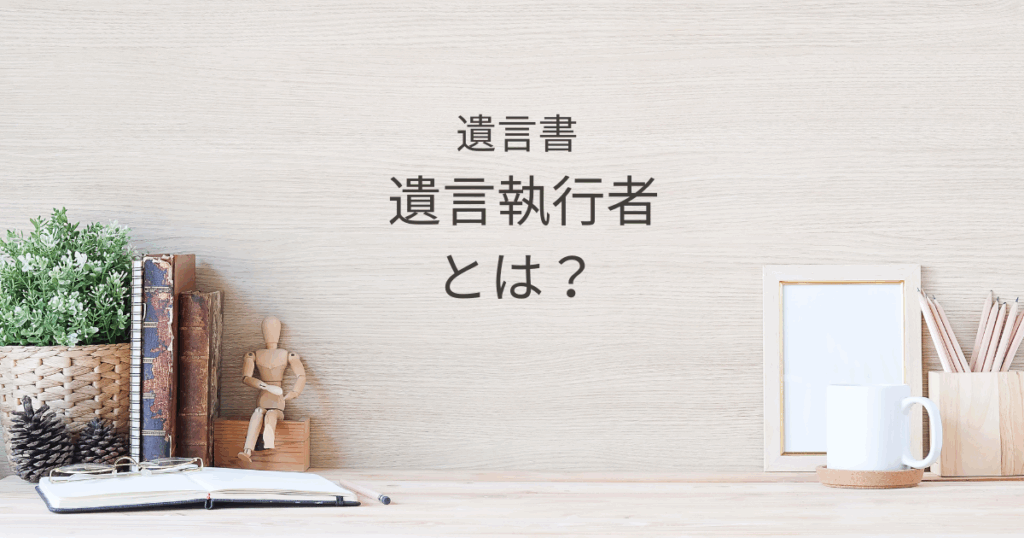
目次
遺言執行者とは?誰を選ぶべきかとその役割・責任について丁寧に解説
「遺言執行者って具体的に何をする人なの?」
「家族にお願いしても大丈夫?」
遺言書を作成するとき、必ず検討したいのが「遺言執行者」の選任です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実際に手続きとして実現する責任ある立場。
適切な人を選ばないと、相続人同士で争いになったり、手続きが進まないリスクがあります。
この記事では、遺言執行者の基本的な役割や選任方法、注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する権限をもつ人のことです。
民法第1012条では次のように定められています。
「遺言執行者は、相続人その他の利害関係人に対して遺言を執行する権利義務を有する。」
簡単にいえば、遺言書を「書いただけ」で終わらせず、現実に手続きを進める責任者です。
遺言執行者の主な役割
遺言執行者は、遺言書の内容によってさまざまな手続きを行います。
-
財産目録の作成
-
不動産の相続登記
-
預貯金の払い戻し
-
遺贈の実行
-
相続人廃除の手続き
-
認知の届出
「相続人全員の同意が必要な場面でも、遺言執行者が単独で進められる」という大きな権限があります。
遺言執行者を指定するメリット
-
遺言の実現がスムーズになる
相続人全員の協議が不要なため、手続きが迅速です。 -
相続人の負担を軽減できる
複雑な手続きを代行できます。 -
トラブルを防ぎやすい
「誰が執行するか」を明確にすることで争いを減らせます。
遺言執行者を指定しないとどうなる?
遺言執行者を指定しない場合、相続人全員で協議して手続きを進める必要があります。
しかし相続人間の意見が合わないと、遺言が実行できない恐れもあります。
特に、認知や相続人廃除などの手続きは「遺言執行者がいないとできない」ため注意が必要です。
誰を遺言執行者に選ぶべきか?
遺言執行者は相続人や第三者、専門家を指定できます。
家族を選ぶ場合
メリット
-
事情をよく知っている
-
費用負担が少ない
注意点
-
相続人同士の感情的対立が起こることも
-
専門的手続きの負担が大きい
専門家を選ぶ場合(行政書士・司法書士・弁護士)
メリット
-
中立性が高い
-
手続きに慣れている
-
書類作成や登記もスムーズ
注意点
-
報酬が必要(目安:10〜30万円程度)
遺言執行者の選任方法
遺言執行者は遺言書で指定できます。
「遺言執行者を〇〇に指定する」と明記するだけで効力があります。
もし遺言書で指定がない場合は、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てることも可能です。
実例|遺言執行者が指定されて安心できたケース
事例① 長男を執行者に指定
父が長男を遺言執行者に指定。葬儀後すぐに手続きを進め、全ての相続が2か月で完了。
事例② 専門家を指定
兄弟仲が良くないため、行政書士を執行者に指定。中立的に対応し、トラブルなく手続き完了。
Q&A|よくある質問
Q. 遺言執行者は辞退できますか?
A. はい、就任前に辞退も可能です。就任後に正当な理由があれば辞任も可能です。
Q. 遺言執行者に報酬は必要?
A. 相続人や家族なら不要な場合もありますが、専門家は報酬が発生します。
Q. 複数人を遺言執行者にできますか?
A. はい、複数人を指定できます。その場合は役割分担を明記するとスムーズです。
公正証書遺言と遺言執行者
遺言執行者を確実に指定するためには、公正証書遺言がおすすめです。
-
法的に有効な形で執行者を記載できる
-
公証役場に保管され安心
-
証人がいるため無効リスクが低い
Kanade行政書士事務所では、公正証書遺言作成から執行者受任まで一貫してお手伝いします。
まとめ|遺言執行者を決めることで安心を残す
遺言執行者は、あなたの最終意思をきちんと実現する存在です。
「誰に任せるか」を早めに考え、遺言書にしっかり記載することで、残される方々の安心につながります。
不安があれば、専門家に相談しながら進めましょう。
ご相談ください
Kanade行政書士事務所では、遺言執行者の指定・遺言書作成・手続きサポートを一貫してご提供しています。
お気軽にご相談ください。
▶関連記事