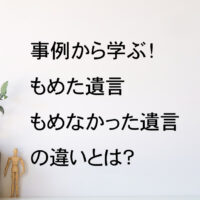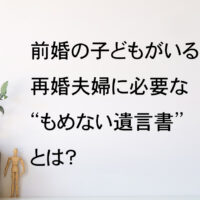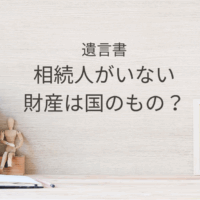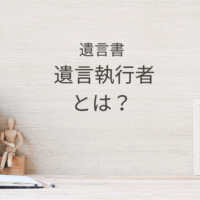コラム
5.202025
寄与分とは?相続人間の不公平を防ぐために知っておきたい基礎知識
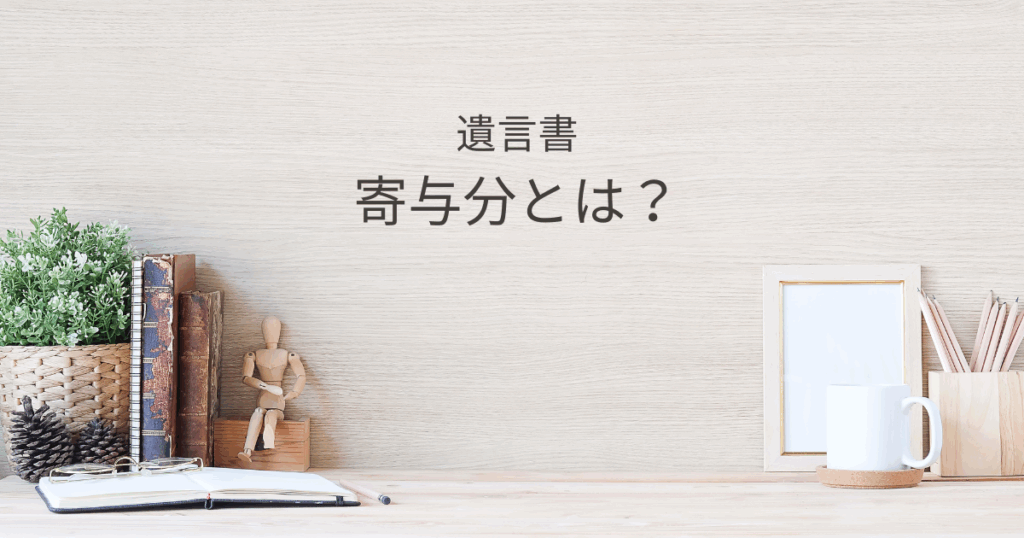
目次
寄与分とは?相続人間の不公平を防ぐために知っておきたい基礎知識
「親の介護を一人で担ってきたのに、相続は兄弟で均等って納得いかない…」
「事業を手伝って家計を支えてきたが、評価されるんだろうか…」
相続は「財産を分ける」手続きであると同時に、家族の長い歴史を振り返る場面でもあります。
特に介護や家業を支えてきた人がいる場合、その貢献を公平に反映するのが「寄与分(きよぶん)」という制度です。
この記事では、寄与分の考え方や手続き、注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
寄与分とは?
寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産維持や増加に特別の貢献をした相続人に対して、相続分を増やす制度です。
法律上の位置づけ
民法第904条の2で次のように定められています。
「共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供、療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、その寄与分を考慮して相続分を定める。」
具体例
-
長期間の療養看護
-
被相続人の事業を無給で手伝った
-
資金援助をして財産の増加に貢献した
寄与分と扶養義務の違い
「親の面倒をみるのは当たり前では?」と思う方も多いでしょう。
確かに、扶養義務(民法877条)がありますが、それを超える特別の貢献があった場合にのみ寄与分が認められます。
ポイント
-
日常的な扶養 → 寄与分に該当しない
-
特別な貢献 → 寄与分として考慮される可能性
寄与分の計算方法
寄与分の評価は、以下の3つを考慮して判断されます。
-
寄与の内容
-
寄与の程度
-
被相続人の財産の増加額
例:10年間無報酬で介護した場合
→ 市場価格換算で月20万円×120か月=2,400万円
→ 全額認められるわけではなく、事情を考慮し相当分を調整
最終的な金額は、相続人全員の協議か家庭裁判所の調停・審判で決まります。
手続きの流れ
-
遺産分割協議
相続人全員で話し合い、寄与分を認めるか決める。 -
協議が整わない場合
家庭裁判所に調停・審判を申し立てる。
注意点
-
協議が整わないときは期限(相続開始を知ったときから1年以内)に注意
-
書類や証拠(領収書・日誌・写真)を揃えておくことが重要
実例|寄与分が争点になったケース
事例① 長男の介護を評価
母を10年以上介護した長男が、他の兄弟から寄与分を否定され調停へ。
家計簿や訪問看護記録を提出し、約1,500万円の寄与分が認められた。
事例② 事業貢献が寄与分に
亡父の商店を無報酬で支えた長女が寄与分を請求。
利益向上に貢献した証拠を提示し、財産の15%が加算された。
Q&A|よくある質問
Q. 寄与分は遺言で指定できますか?
A. はい、遺言で寄与分に相当する財産を与える内容を記載可能です。
Q. 家庭裁判所でどのくらいの期間かかりますか?
A. 調停は平均3〜6か月、審判は6か月以上かかる場合もあります。
Q. 証拠はどのように準備すればいいですか?
A. 日誌、領収書、関係者の証言など、客観的に裏付けられる資料が重要です。
寄与分と遺言書の関係
寄与分は相続発生後に請求するのが基本ですが、遺言書で生前に配慮することも可能です。
「長男の介護に感謝し、自宅を遺贈する」と明記すれば、相続トラブルを防ぎやすくなります。
公正証書遺言を活用しよう
遺言で寄与分に配慮する場合は、公正証書遺言がおすすめです。
-
内容の不備を防げる
-
法的効力が高い
-
証拠性が強い
Kanade行政書士事務所では案分作成から証人手配まで一貫サポートいたします。
まとめ|寄与分を正しく理解し、公平な相続へ
寄与分は、家族の中で「見えにくい貢献」をきちんと評価する制度です。
トラブルを防ぐためには、
-
事前に証拠を整理する
-
遺言書で意思を明確にする
-
専門家に相談する
ことが大切です。
不公平感を残さない相続のために、準備を進めていきましょう。
▶ ご相談ください
Kanade行政書士事務所では、寄与分を含む相続手続き・遺言書作成を丁寧にお手伝いしています。
安心できる準備を一緒に考えましょう。
▶関連記事