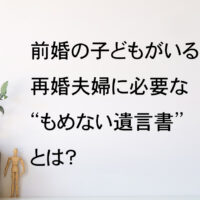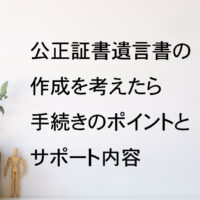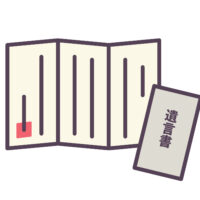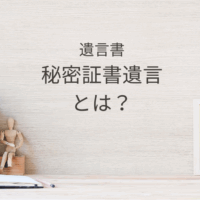コラム
5.182025
遺言書で財産を寄付したい|自治体・NPO法人への遺贈の手続きと注意点
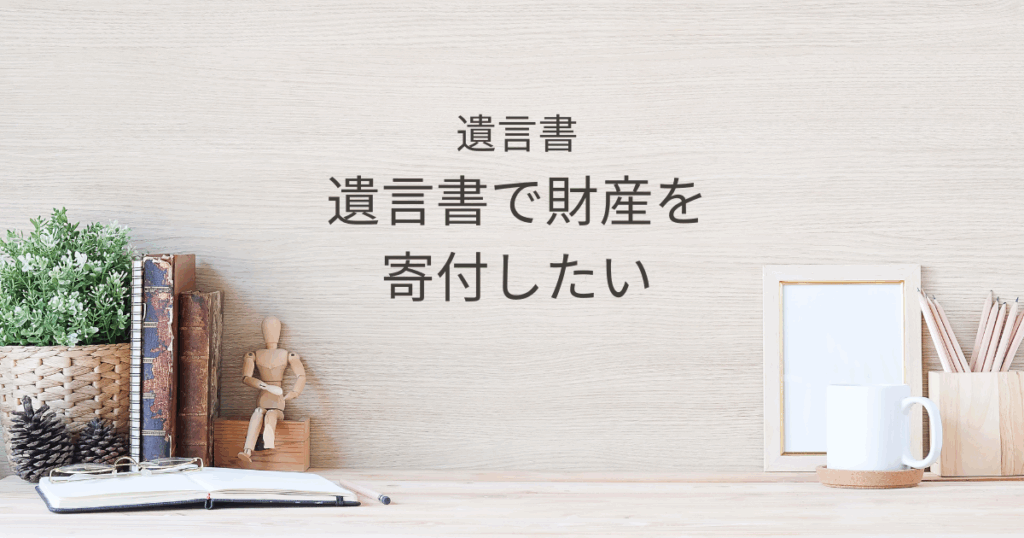
目次
遺言書で財産を寄付したい|自治体・NPO法人への遺贈の手続きと注意点
「遺言書で地域や社会に貢献したい」
「大切にしてきた財産を誰かのために役立てたい」
人生の集大成として、財産を自治体やNPO法人に寄付する「遺贈寄付」を考える方が増えています。
しかし、遺言書の書き方や手続きに不備があると、希望通りに寄付できなかったり、家族とのトラブルが生じる場合もあります。
この記事では、遺言書を活用して財産を寄付する方法と、注意すべきポイントを行政書士の視点から解説します。
遺贈寄付とは?
遺贈寄付とは、遺言書を通じて、特定の団体や地域へ財産を寄付することです。
対象は多岐にわたります。
-
自治体(市町村・県)
-
公益法人(社会福祉法人・学校法人など)
-
認定NPO法人
-
公益財団法人
「人生の感謝を形にする寄付」として、多くの方が遺贈寄付を選んでいます。
遺贈と生前贈与の違い
遺贈寄付は「亡くなったときに効力が発生する」寄付です。
一方、生前贈与は存命中に財産を移転します。
| 項目 | 遺贈 | 生前贈与 |
|---|---|---|
| 効力発生 | 死亡時 | 贈与契約成立時 |
| 税金 | 相続税 | 贈与税(非課税枠あり) |
| 手続き | 遺言書が必要 | 贈与契約書が必要 |
相続税と贈与税の違いがあるため、寄付のタイミングを検討することも大切です。
遺言書で寄付する場合の種類
遺言書で寄付する際、表現や種類を明確にする必要があります。
特定遺贈
財産を特定して遺贈する方法。
例:「私の預貯金のうち1,000万円を◯◯市に寄付する。」
対象や金額がはっきりしているため、執行がしやすいメリットがあります。
包括遺贈
財産全体の一定割合を寄付する方法。
例:「全財産の30%を公益財団法人〇〇に遺贈する。」
包括遺贈は負債も承継する可能性があり、注意が必要です。
寄付先の確認が重要
寄付先が法人の場合、解散していたり受け取りを辞退されるケースもあります。
寄付先を事前に確認するポイント
-
受け入れの意向があるか
-
寄付の手続きをどの部署が行うか
-
使途の希望をどの程度反映できるか
特にNPO法人の場合、寄付の受け入れ体制が整っていない場合もあるため、事前確認が大切です。
注意点|寄付による遺留分侵害
相続人には「遺留分」という最低限の取り分があります。
例:
配偶者と子がいる場合、全財産をNPO法人に寄付する遺言は、相続人から遺留分侵害請求を受ける可能性があります。
事前に遺留分に配慮した設計を行い、家族への説明も準備しておくと安心です。
公正証書遺言での作成がおすすめ
寄付の遺言書は、表現や手続きの誤解が大きなリスクになります。
公正証書遺言なら、
-
内容の不備を防げる
-
公証役場で保管される
-
執行者を指定できる
など、多くの安心材料があります。
こんなご相談が増えています
事例① 生まれ育った自治体へ寄付したい
80代男性が「全財産を市の子育て支援に活用してほしい」とご相談。遺言書と市への意向確認をセットで進めました。
事例② NPO法人に寄付を希望
「長年支援した団体に寄付したいが、受け取りが可能か心配」との声。事前に団体に確認し、公正証書遺言で指定しました。
Q&A|よくある質問
Q. 寄付に相続税はかかりますか?
A. 公益法人・自治体は非課税です。認定NPO法人も一定条件で非課税になります。
Q. 寄付先が受け取らなかった場合は?
A. 遺言書に「寄付先が辞退した場合は〇〇に遺贈する」と予備的記載を入れることが可能です。
Q. 財産を複数の団体に分けられますか?
A. はい、特定遺贈を複数設定できます。
まとめ|想いをつなぐ遺贈寄付
遺贈寄付は、人生で大切にしてきた価値観を未来に託す手段です。
誰に何を、どのように遺したいのかを整理し、家族にも理解される形で準備を進めましょう。
ご相談ください
Kanade行政書士事務所では、遺贈寄付を含む遺言書の作成を丁寧にサポートしています。
自治体・NPO法人への寄付手続きも安心してお任せください。