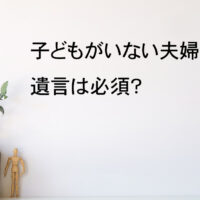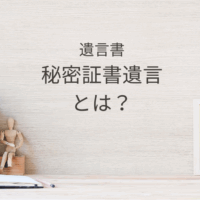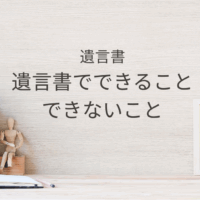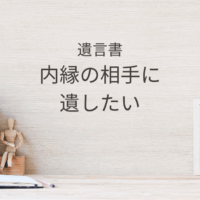コラム
5.172025
遺言書の撤回や変更はできる?訂正方法と注意点をわかりやすく解説
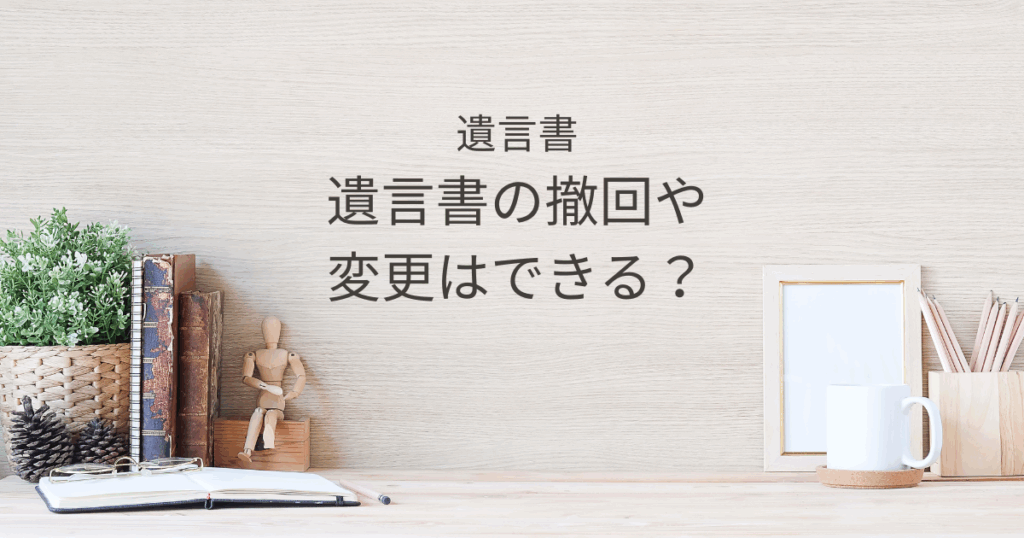
目次
遺言書の撤回や変更はできる?訂正方法と注意点をわかりやすく解説
「遺言書って、一度書いたら絶対に変えられないんですか?」
「気持ちが変わったとき、どう訂正すればいいんでしょう?」
遺言書の相談を受けると、こうしたご質問をよくいただきます。
遺言書は「最終意思を記録するもの」として非常に強い効力を持ちますが、気持ちや事情が変わることも当然あります。
そのため、法律は遺言書を自由に撤回・変更できる仕組みを用意しています。
ただし、訂正方法を誤ると「その部分だけ無効」「すべて無効」になることもあります。
この記事では、遺言書の撤回・変更の方法と注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
遺言書は撤回・変更できる
民法では、遺言者本人がいつでも遺言を撤回・変更できると定められています。
つまり「一度書いたら絶対に変えられない」ということはありません。
民法1022条
「遺言者は、いつでもその遺言の全部または一部を撤回することができる。」
人生の状況や家族構成が変わることを考えると、こうした柔軟性は大きな安心材料です。
撤回と変更、どう違う?
撤回とは
遺言書を無効にすることを「撤回」といいます。
たとえば、
-
新しい遺言書を作り、旧遺言書をすべて撤回すると明記する
-
遺言書を破棄する(燃やす・破る)
こうした行為で撤回が成立します。
変更とは
遺言書の一部だけを修正・書き換えることを「変更」といいます。
たとえば、
-
特定の財産の受取人を変更する
-
財産の分配割合を変える
ただし、自筆証書遺言の場合は訂正方法に厳密なルールがあります。
自筆証書遺言の訂正方法
自筆証書遺言を訂正するときは、以下の3点が必須です。
-
訂正箇所を二重線で抹消
-
訂正した場所に署名
-
訂正内容を明記
この要件を満たさないと、訂正部分は無効になります。
例:
「第2条 相続分を3分の1とする」の「3分の1」を「2分の1」に変える場合
→ 元の記載を二重線で消し、訂正を記載し、署名する
訂正が複雑な場合や全体を見直したい場合は、新しい遺言書を作成するほうが確実です。
公正証書遺言の変更方法
公正証書遺言は自分で書き換えはできません。
変更したいときは再度公証役場に行き、新しい遺言書を作成する必要があります。
新しい公正証書遺言を作れば、古いものは自動的に効力を失います。
撤回・変更の注意点
1. 部分的な撤回は可能
遺言書の全部を撤回する必要はありません。
「第3条の遺贈を撤回する」など、一部だけ無効にすることもできます。
2. 撤回した証拠が必要になる場合がある
たとえば遺言書を破棄した場合、「本当に本人が破棄したのか」が争われることがあります。
可能であれば、公正証書遺言を作り直す形が最も安全です。
3. 新しい遺言書が優先される
複数の遺言書が残っている場合、最新の日付のものが優先されます。
古い遺言書を撤回する記載がなくても、矛盾する部分は新しい内容が有効になります。
こんなときは要注意
事例① 訂正のルールを守らず無効に
自筆証書遺言で相続人の名前を書き換えたが、署名・訂正の明記がなく無効になったケース。
事例② 古い遺言書を破棄した証拠がなく争いに
新しい遺言書を作る前に古いものを破棄したが、破棄を示す証拠がなく無効と判断された。
事例③ 遺言書が複数残り混乱
自筆証書遺言と公正証書遺言が残され、内容が矛盾し相続人同士でトラブルに。
Q&A|よくある質問
Q. 遺言書を訂正するとき、専門家に依頼する必要はありますか?
A. 自筆証書遺言の場合は本人が行う必要がありますが、公正証書遺言の作成は公証役場に相談するほうが確実です。
Q. 新しい遺言書を作ったら、古いものを破棄するべきですか?
A. はい、残しておくと内容の混乱を招くため、破棄をおすすめします。
Q. 何度でも変更できますか?
A. はい、遺言者本人の意思で何度でも変更・撤回が可能です。
公正証書遺言が安心な理由
遺言書の変更・撤回で最もトラブルが少ない方法は、公正証書遺言を新たに作成することです。
-
内容の不備がない
-
公証役場に保管される
-
最新の意思が確実に反映される
Kanade行政書士事務所では、公証役場との調整や証人手配もサポートしています。
まとめ|変わる気持ちに対応できる遺言書
遺言書は「そのときの最終意思」を形にするものです。
人生の変化に合わせて、内容を更新し続けることができます。
「書いたけれど気が変わったかも」「家族構成が変わった」
そう思ったときは、遠慮なく見直しを検討してください。
ご相談ください
Kanade行政書士事務所では、遺言書の作成から変更・撤回まで一貫してお手伝いしています。
安心の準備を、一緒に進めましょう。