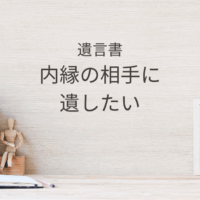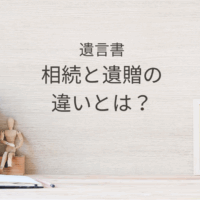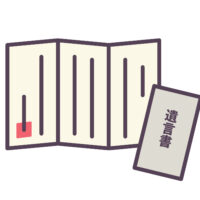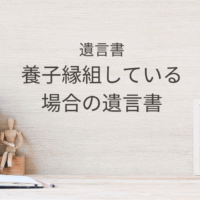コラム
5.62025
自筆証書遺言とは?自分で書く遺言書のメリット・注意点をやさしく解説
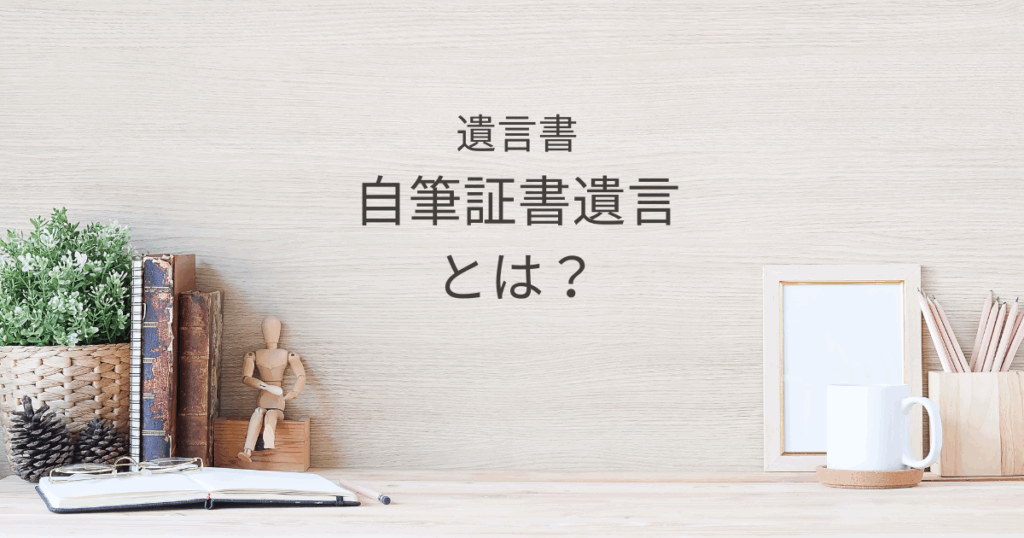
目次
自筆証書遺言とは?基本ルール・失敗例・保管制度まで専門家が解説
遺言書は、人生の最終意思を遺すための大切な手段です。中でも「自筆証書遺言」は、自分ひとりで作成できる最も手軽な遺言方式として、多くの方が一度は検討されます。
しかし、自筆で書ける気軽さがある一方で、書き方や形式を間違えると「無効」になってしまうことも。
この記事では、自筆証書遺言の基本的なルールから、よくある失敗例、メリット・デメリット、そして2020年からスタートした法務局の保管制度まで、専門家の視点でわかりやすく解説します。
自筆証書遺言の基本ルールとは?
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を手書きし、日付・氏名・押印をして作成する遺言書のことです。遺言書として法的に有効とするには、以下のルールを守る必要があります。
【基本的な作成ルール】
-
全文を自書すること(ワープロや代筆は不可)
-
日付を明記すること(「令和〇年〇月吉日」など曖昧な記載はNG)
-
氏名を署名し、押印すること(認印でも可能、実印が望ましい)
-
財産目録のみ、パソコンで作成可能(ただし署名・押印が必要)
自筆証書遺言のメリットとデメリット
【メリット】
-
費用がかからない(自分で書くだけなので無料)
-
自宅で手軽に作成できる
-
誰にも知られず作成可能(秘密性が高い)
-
思い立ったときに書き直せる自由さ(複数の遺言書がある場合、日付の新しいものが有効)
【デメリット】
-
書式や内容の不備で無効になるリスク
-
紛失・未発見の可能性がある
-
相続開始後に家庭裁判所で「検認」が必要
よくある失敗例とその対策
自筆証書遺言でよく見られる失敗は、次のようなものです。
■ 日付が不明確
例:「〇月吉日」「春の日に」など → 無効になる可能性
→ 対策:年月日を正確に記載(例:令和7年4月1日)
■ 財産の特定が不十分
例:「預金すべてを長男に」→ 銀行名や支店名が曖昧
→ 対策:銀行名・支店名・口座番号まで記載
■ 誰に何を遺すかが不明確
→ 相続人の氏名・続柄を明記し、誰に何を遺すかを明確に書くことが大切です。
👉 具体的な事例が気になる方は
宇都宮の事例から学ぶ!もめた遺言・もめなかった遺言の違いとは?
もあわせてご覧ください。
検認と法務局の保管制度について
自筆証書遺言は、相続が開始した後に家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければなりません。
【検認とは?】
-
遺言書の状態や内容を確認し、改ざんや隠匿を防ぐ手続き
-
相続登記や銀行手続きなどに必須となることが多い
-
通常、数週間〜数か月の時間がかかる
【法務局の保管制度】
2020年から、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえる制度がスタートしました。
【メリット】
-
紛失・改ざんの心配がない
-
家庭裁判所の検認が不要
-
死後、相続人が法務局でスムーズに内容を確認できる
【注意点】
-
内容の有効性については法務局ではチェックしない
-
手続きは本人が出頭して行う必要がある
専門家にできること・できないこと
自筆証書遺言は本人が書くものですが、行政書士をはじめ専門家のサポートを受けることで、形式不備や内容の誤解を防ぐことができます。
【専門家ができること】
-
書式や必要項目のチェック
-
財産目録・家系図の整理
-
文言の整理とアドバイス
【行政書士が対応できないこと(各士業の領域)】
-
相続登記 → 司法書士
-
相続税の申告 → 税理士
-
裁判所での検認手続き代理 → 司法書士・弁護士
相続全体の流れを見据えながら、信頼できる専門家に早めに相談しておくことが、後悔しない一歩です。
まとめ|自筆証書遺言を確実に遺すために
自筆証書遺言は、手軽さと自由度が魅力の遺言形式です。
しかし、ただ「書けた」だけでは不十分。
本当に大切なのは、
「法的に有効で、家族にとってもわかりやすい形で残すこと」です。
形式不備・内容の誤解・紛失といったリスクを避けるためにも、不安がある場合は一度専門家に確認してもらうことをおすすめします。