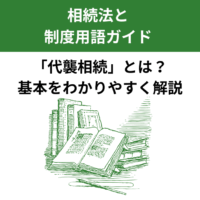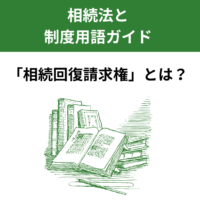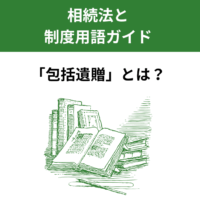- Home
- 相続法と制度用語ガイド
- 「遺留分侵害額請求権」とは?旧制度との違いも含めて徹底解説
コラム
11.192025
「遺留分侵害額請求権」とは?旧制度との違いも含めて徹底解説
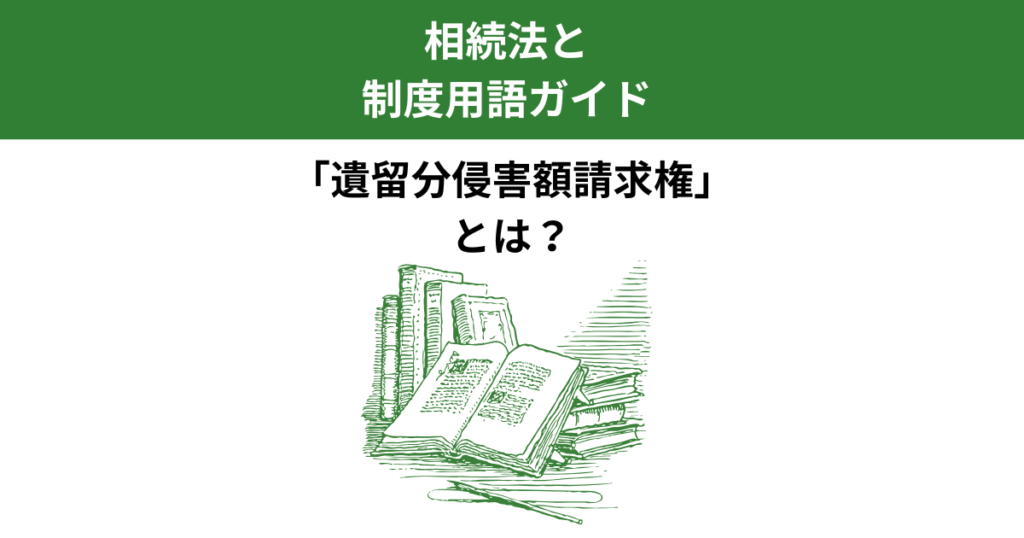
「遺留分侵害額請求権」とは?旧制度との違いも含めて徹底解説
相続では、故人の意思を尊重するために「遺言」が用いられますが、遺言によって相続人の生活が脅かされないようにするための仕組みとして、「遺留分」 が法律で定められています。
2019年7月の民法改正により、遺留分制度には大きな変更がありました。特に重要なのが、旧制度の「遺留分減殺請求」から、現在の 「遺留分侵害額請求」 へと仕組みが変わった点です。この記事では、遺留分とは何か、遺留分侵害額請求はどのように行うのか、旧制度との違いまでを整理して解説します。
目次
1.遺留分とは?誰にどれだけ認められるのか
遺留分とは、一定の相続人に保障された 最低限の取り分 のことです。故人が遺言や生前贈与で財産を処分しても、遺留分を侵害された相続人はその侵害額の支払いを請求できます。
● 遺留分が認められる人
遺留分があるのは次の相続人に限られます。
- 配偶者
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(父母):子がいない場合のみ
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。
● 遺留分の割合
遺留分の割合は民法で定められています。
- 配偶者+子が相続人:1/2
- 配偶者のみ・子のみ:1/2
- 直系尊属のみ:1/3
これは、相続財産に対する「遺留分権利者全体の合計割合」です。
2.遺留分侵害額請求権とは?(現行制度の基本)
2019年7月1日以降の相続について適用される制度です。遺留分が侵害された相続人は、金銭で遺留分相当額を請求できる権利 を「遺留分侵害額請求権」といいます。
● 現行制度のポイント
- 対応手段は 金銭請求のみ
- 不動産や株式を取り戻すことはできない
- 相手方(受贈者・受遺者)に対して請求する
- 請求の方法は「通知書(内容証明郵便など)」が一般的
- 金銭の支払い方法は当事者間の協議で定める
遺留分侵害額請求権は、「物や権利を取り戻すものではなく、侵害された分を金銭で補填する制度」に変わりました。
3.旧制度との違い:遺留分減殺請求との決定的な差
2019年以前の遺留分制度は、「遺留分減殺請求」 という性質の異なる制度でした。
比較すると次のように違いがあります。
●(1)旧:減殺請求 → 物権的効果(共有化)
旧制度では、遺留分が侵害されている場合、対象の財産を「取り戻す」ことが可能で、不動産の場合は強制的に共有状態が発生するという問題点がありました。
【問題点】
- 受遺者が住んでいる不動産が突然共有になる
- 共有解消のために売却・分割が必要
- 実務が非常に複雑
- 受遺者とのトラブルが起きやすい
●(2)現行:侵害額請求 → 金銭債権のみ
民法改正により、遺留分権利者は金銭での補填を請求する権利だけを持つことになりました。
【改善点】
- 不動産の共有化が発生しない
- 金銭支払いで解決するため実務が整理しやすい
- 財産管理のトラブルが減少
- 第三者にも分かりやすく、法的安定性が高い
このように、現行制度は 実務負担を軽減し、紛争を減らすこと を目的に設計されています。
4.遺留分侵害額の計算方法(正確な要点のみ)
遺留分侵害額は次のように算出します。
① 相続財産(遺産)を確定する
現金・預貯金・不動産・有価証券などを評価。
② 特別受益(生前贈与)を加算する
原則、死亡前10年以内の贈与が対象。
(例外あり:相続人への生活費・通常の贈与は除外)
③ 債務を控除する
借金や未払金などを差し引く。
④ 遺留分の割合を乗じる
⑤ すでに受け取っている財産を控除する
この結果が 遺留分が侵害されている金額=請求できる金額 となります。
【補足】相続税の生前贈与加算ルールは“3年→7年”へ段階的に拡大
遺留分では「原則・死亡前10年以内の生前贈与」が算入対象となりますが、
相続税の生前贈与加算ルールはまったく別の制度です。
従来、相続税では「死亡前3年以内の贈与」が加算されていましたが、
令和5年度改正により、加算期間が段階的に7年へ拡大することになりました。
● 相続税での主な改正点(令和5年度改正)
- 2024年1月1日以降の贈与から、手当期間が従来の3年から段階的に延長
- 2027〜2030年に相続発生した場合
→「2024年1月1日〜死亡日」までの贈与が一括加算
- 2031年(令和13年)以降の相続
→「死亡前7年以内」の贈与が対象
- 4〜7年前の贈与のうち100万円までは加算しない経過措置あり
✔ 相続税対策としての生前贈与は、従来より効果が縮小へ
加算期間が延びるほど、「早めに贈与しても相続税で加算されてしまう可能性」が高くなります。そのため、これからは 贈与記録の正確な管理がより重要 となります。
このように、遺留分(10年ルール)と相続税(3年→7年ルール)は完全に別の制度 であり、目的・計算方法・対象期間のすべてが異なる点を押さえておくと、誤解なく理解できます。
5.遺留分侵害額請求には期限がある
遺留分侵害額請求権には「時効」があります。
- 侵害を知った時から 1 年
- 相続開始から 10 年
どちらか早い方で時効となります。「遺留分を請求するなら早めに動く必要がある」というのは、このためです。
6.遺留分侵害額請求の一般的な流れ
※ 法的代理や交渉は弁護士にご相談ください。
- 相続財産の調査
- 生前贈与の確認
- 遺留分計算
- 相手方へ意思表示(通知)
- 金額や支払い方法の協議
- 必要に応じて調停・訴訟へ(弁護士が担当)
※ 法的代理や交渉は弁護士にご相談ください。
請求は「相手方に意思表示が到達する」ことで効力を持ちます。
7.遺留分侵害額請求が利用される典型例
- 特定の相続人に全財産を相続させる遺言
- 内縁関係・第三者に多くの財産を遺贈する遺言
- 一部の子だけに多額の生前贈与
- 家業を継ぐ者に不動産が集中している
こうした場合、他の相続人が遺留分侵害額請求を検討することが多いです。
8.まとめ:現行制度は“金銭で調整する”仕組みに統一された
遺留分侵害額請求制度は、旧制度の複雑さを解消し、金銭での解決を原則とするシンプルな仕組みに改められました。
- 不動産や財産を「取り戻す」制度ではない
- 金銭債権として請求する
- 時効は原則1年
- 生前贈与も含めて計算される
- 遺言による財産偏在を一定程度調整する仕組み
遺留分は“家族の生活を守るための最低限の保障”です。遺言や生前贈与がどれほど自由であっても、法律は一定のバランスを確保する仕組みを用意しています。