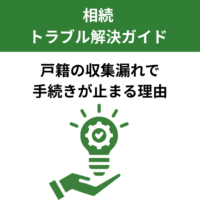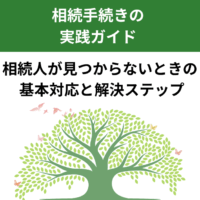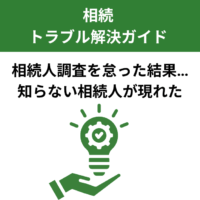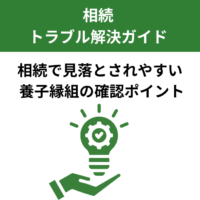- Home
- 相続トラブル解決ガイド
- 自筆遺言が方式不備で無効になりかけたケースから学ぶ相続準備の大切さ
コラム
11.62025
自筆遺言が方式不備で無効になりかけたケースから学ぶ相続準備の大切さ
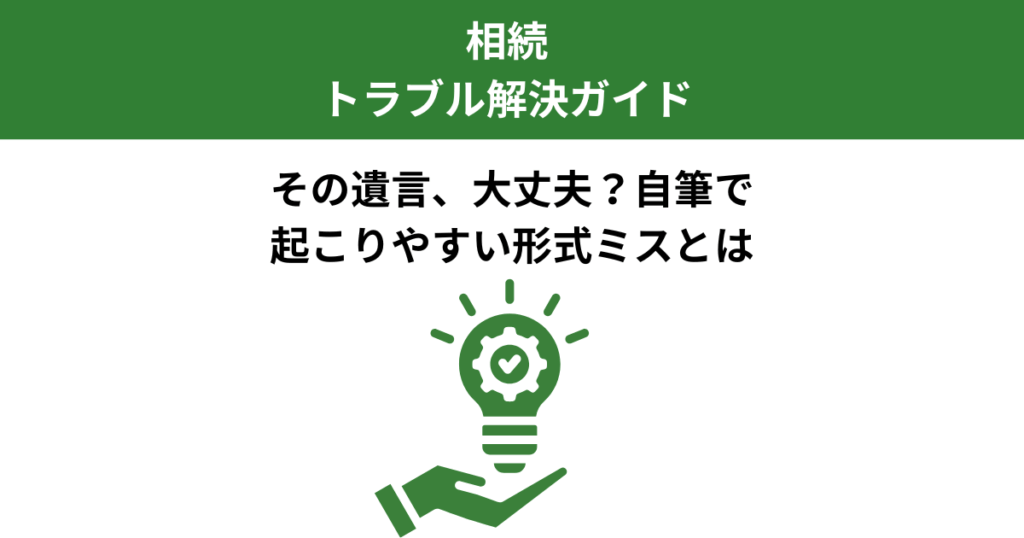
「自筆で書いた遺言があるから安心」そう思っていても、形式上の不備(方式不備)によって、遺言が無効と判断されてしまうケースは少なくありません。
実際に、「この自筆遺言で問題ありませんか?」というご相談が寄せられることがあります。拝見すると、日付の記載が抜けていたり、財産目録に押印がなかったりと、このままでは法的に効力を持たない可能性が高い内容でした。
ご本人は「気持ちはきちんと書いたつもりだった」とお話しされていましたが、形式のほんのわずかな違いが、想いを伝える力を失わせてしまうことがあります。
今回は、そうした実例をもとに、遺言の有効性確認と早めの備えについてわかりやすく解説します。
目次
事例 ― 自筆遺言が“形式不備”となる場合のご相談
ご相談者Aさんは、「自分の財産を長男に相続させたい」という思いから、自分で遺言書を作成していました。
しかし、確認したところ、
-
日付が「令和〇年〇月」となっており、日にちの記載が抜けていた
-
財産目録をパソコンで作成していたものの、各ページに署名のみで押印がなかった
これらの点から、仮に相続発生後に開封されても、方式不備により無効と判断される可能性が高い内容でした。
Aさんご自身は「内容は間違っていない」と感じていたそうですが、長男以外にも兄弟がいたため、後の誤解や争いを避けたいという思いから、最終的には公正証書遺言での作成を検討する方向で整理を進めました。
「これでようやく安心できた」と笑顔で帰られたAさんの姿が印象的で、遺言は「書いただけ」ではなく、「きちんと想いが伝わるか」が大切だと改めて感じた事例でした。
自筆遺言が無効とされる主な原因
自筆証書遺言は、民法第968条により、一定の方式を満たすことが求められています。
よくある不備の例として、次のようなものがあります。
-
日付・氏名・押印のいずれかが欠けている
-
財産目録をパソコンで作成したが署名押印をしていない
-
訂正方法が法的要件を満たしていない
-
書いたあとに加筆・修正をしても訂正印がない
これらのいずれかがあるだけで、遺言書全体が無効になるリスクがあります。
無効を防ぐための3つの備え
-
形式の最終チェックを行う
→ 年月日・署名・押印が揃っているかを自分で確認。 -
財産目録の扱いに注意する
→ パソコン作成の場合、各ページ(両面記載の場合は両面)に署名押印を忘れずに。 -
法務局の遺言書保管制度を活用する
→ 保管申請時に形式要件を確認でき、紛失や改ざん防止にも役立ちます。
専門家に相談する意味
遺言書の作成は、形式を整えるだけでなく、「家族に伝わる形」で残すことが何より重要です。
専門家に相談することで、形式面の確認だけでなく、相続人関係や財産内容の整理など、事前準備からサポートを受けることができます。
「書いたつもり」が「伝わらなかった」にならないように、作成後のご相談もおすすめです。
まとめ ― 書くことよりも「伝わること」を意識して
遺言書は「書くこと」が目的ではありません。本当の目的は、家族が迷わずに想いを受け取れるようにすることです。
形式の一つひとつを丁寧に確認しておくことで、その想いがしっかりと未来へ届きます。
整った準備が、家族への何よりの思いやりとなるのかもしれません。