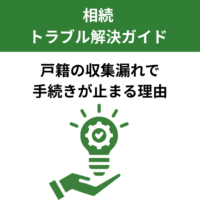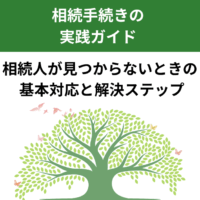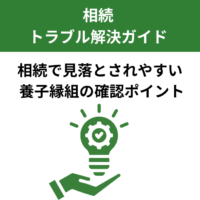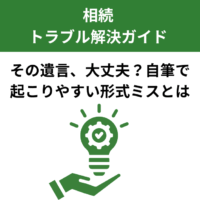- Home
- 相続トラブル解決ガイド
- 遺言書の文言ミスに注意|相続で誤解を招かないための基本と対策
コラム
10.302025
遺言書の文言ミスに注意|相続で誤解を招かないための基本と対策
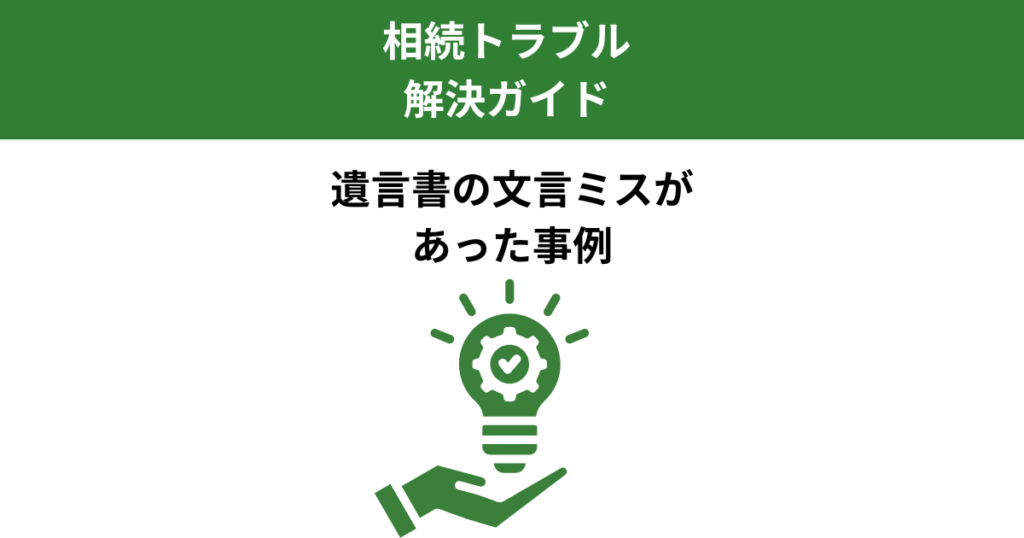
遺言書の文言ミスで相続人同士がトラブルになった相談事例
目次
はじめに:遺言書の「文言」がもたらす思わぬ行き違い
せっかく遺言書を作成しても、その文言の曖昧さや誤りが原因で、家族が混乱してしまうことがあります。
近年、「遺言書はあるのに、手続きがスムーズに進まない」というご相談が増えています。
この記事では、実際にあった事例をもとに、どのような記載ミスがトラブルを招くのか、そしてそれを防ぐためのポイントを分かりやすく解説します。
事例紹介:文言の曖昧さで手続きが滞ったケース
Aさん(故人)は、「私の財産のうち自宅を長男に相続させる」と遺言書に記していました。
ところが、他の相続人は「“財産のうち”とは何を指すのか」「預貯金も含まれるのではないか」と解釈が分かれました。
遺言書の記載内容が不明確だったため、手続きを進めるにあたり関係者間で認識が一致せず、結果的に相続が長期化してしまったのです。
主な原因
-
「財産のうち」といった抽象的な表現で、対象財産が特定されていなかった
-
「自宅」としか書かれておらず、土地・建物の所在や地番などが不明確だった
-
「相続させる」と「遺贈する」の使い分けがされていなかった
このようなケースでは、遺言書自体は有効でも、手続き実務が進まないという状況が起きてしまいます。
よくある文言ミスと注意すべきポイント
① 財産の特定があいまい
「自宅」「預金」「株式」などの表現だけでは、どの不動産や口座を指しているのかが不明確です。
登記簿や通帳の情報をもとに、正確な名称・所在地・口座番号を記載することが望ましいでしょう。
② 用語の混同
「相続させる」と「遺贈する」は似ていますが、相続人かどうかによって使い分けが必要です。
この区別を誤ると、登記や名義変更時に追加の確認が求められることがあります。
③ 訂正や加筆の方式不備
遺言書の訂正や追記には、民法上の方式(訂正印や署名など)が求められます。
誤った修正を行うと、その部分の内容が無効とされることがあります。
防止のための工夫と見直しのすすめ
遺言書を作る際には、法的要件を満たすことはもちろん、読む人にとって分かりやすい構成にすることが大切です。
-
財産を明確に特定し、表現のあいまいさを避ける
-
定期的に内容を見直し、現状に合わせて更新する
-
家族構成や財産状況の変化に応じて、条項を整理する
-
専門家に文面を確認してもらい、誤解が生じないかをチェックする
また、近年では公正証書遺言を選択することで、文言ミスや形式不備を防ぎやすくなっています。形式の整った遺言書は、残された家族にとっても安心です。
弊所でも基本的には文言や法的要件の明確性を確保するため、公正証書遺言を推奨しています。
まとめ:遺言書は“意思”を伝えるための設計図
遺言書の目的は、財産を分けることよりも、「自分の想いを確実に伝え、家族に安心を残すこと」です。
そのためには、内容の正確さ・表現の明確さ・方式の適正が欠かせません。
文言の一つひとつを丁寧に確認し、将来の誤解を防ぐ内容を心がけましょう。
お問い合わせ(栃木県・宇都宮市エリア対応)
Kanade行政書士事務所では、
-
公正証書遺言の作成支援
-
相続手続き全般の書類サポート
を通じて、安心して「想いをかたちにする」お手伝いをしています。