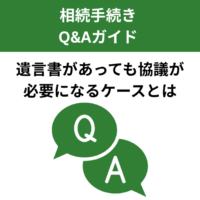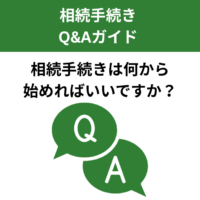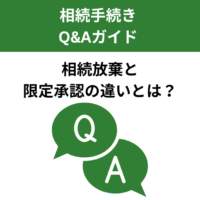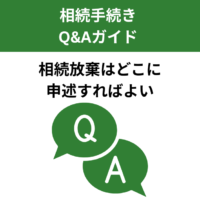- Home
- 相続手続きQ&Aガイド
- 法定相続人とは誰のことですか?
コラム
11.142025
法定相続人とは誰のことですか?
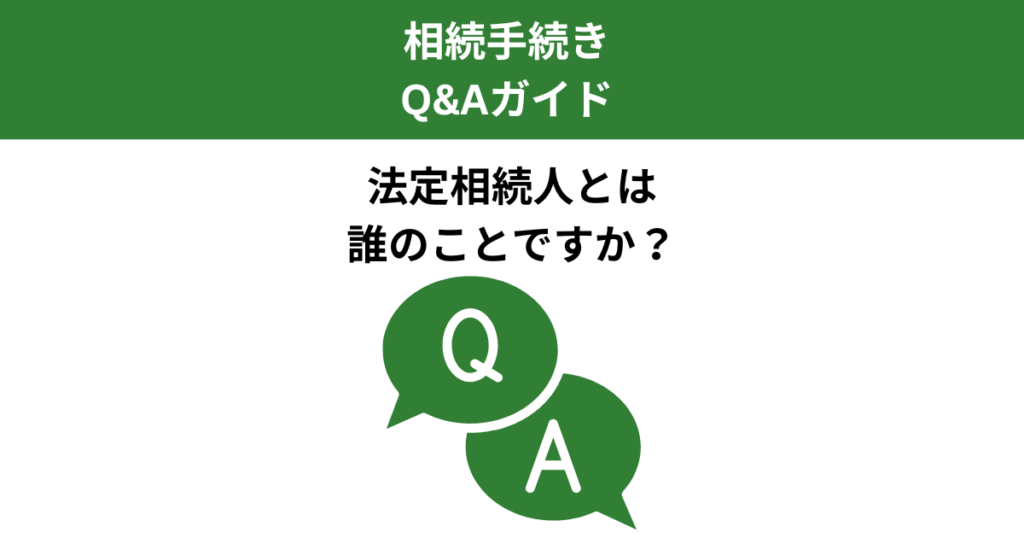
法定相続人とは誰のことですか?
相続手続きを始めると、必ず確認しなければならないのが 「法定相続人は誰か」 という点です。法定相続人とは、法律で「相続する権利を持つ人」と定められた家族のことを指します。
この基本はとても重要ですが、“意外と正確に押さえられていないポイント” のひとつでもあります。ここでは、法定相続人の範囲を分かりやすく整理して解説します。
目次
1.法定相続人になる人は“順位”で決まる
民法では、法定相続人になれる人を次のように「順位」で定めています。
● 第1順位:子ども(または孫)
子どもが相続人となり、
子どもが亡くなっている場合は孫が代わりに相続します(代襲相続)。
● 第2順位:父母(または祖父母)
子ども(孫も含む)がいない場合、父母が相続人になります。
父母が他界していれば祖父母が相続します。
● 第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)
子どもも父母もいないときに兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が相続します(代襲相続)。
2.配偶者は“常に相続人”
順位に関係なく、配偶者(夫または妻)は必ず法定相続人になります。
つまり、
「配偶者 + 第◯順位の相続人」
というセットで考えるのが基本です。
※なお「内縁のパートナー(事実婚)」は、法律上の配偶者ではないため法定相続人には含まれません。
3.“家族の記憶だけ”で判断してはいけない理由
法定相続人を把握するためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍を確認する必要があります。
なぜなら、次のようなケースが実際にあるためです。
-
認知した子がいた
-
前婚の子どもがいた
-
実は兄弟が他県にいた
-
相続人がすでに死亡していた(→代襲相続人がいる)
「家族だから分かっているつもり」という思い込みが、
相続手続きのやり直しやトラブルにつながることがあります。
4.相続人に“なる人”“ならない人”の例
相続人になる人の例
-
配偶者
-
子ども(婚姻外の子も含む)
-
養子
-
父母・祖父母
-
兄弟姉妹・甥・姪
相続人にならない人の例
-
内縁の配偶者
-
子の配偶者(義理の娘・義理の息子)
-
孫でも、子が生存している場合
-
友人・知人
-
事実婚のパートナー
※「相続人でない人に財産を残したい」場合は遺言が必要になります。
5.まとめ ― 法定相続人を“正確に把握すること”が相続の第一歩
相続手続きでは、法定相続人が1人でも漏れていると、遺産分割は成立しません。
-
まずは順位の基準を知る
-
配偶者は必ず相続人
-
家族の記憶ではなく戸籍で確認する
-
認知・養子・代襲相続に注意する
この基本を押さえておくことで、相続手続きがスムーズに進み、後のトラブルも防ぎやすくなります。