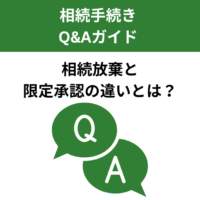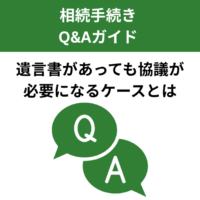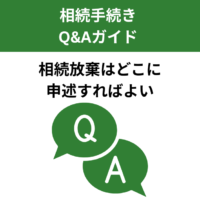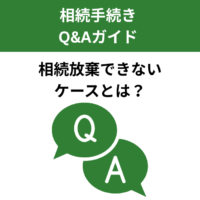- Home
- 相続手続きQ&Aガイド
- 相続手続きは何から始めればいい?最初に確認すべきポイントと進め方の全体像
コラム
10.242025
相続手続きは何から始めればいい?最初に確認すべきポイントと進め方の全体像
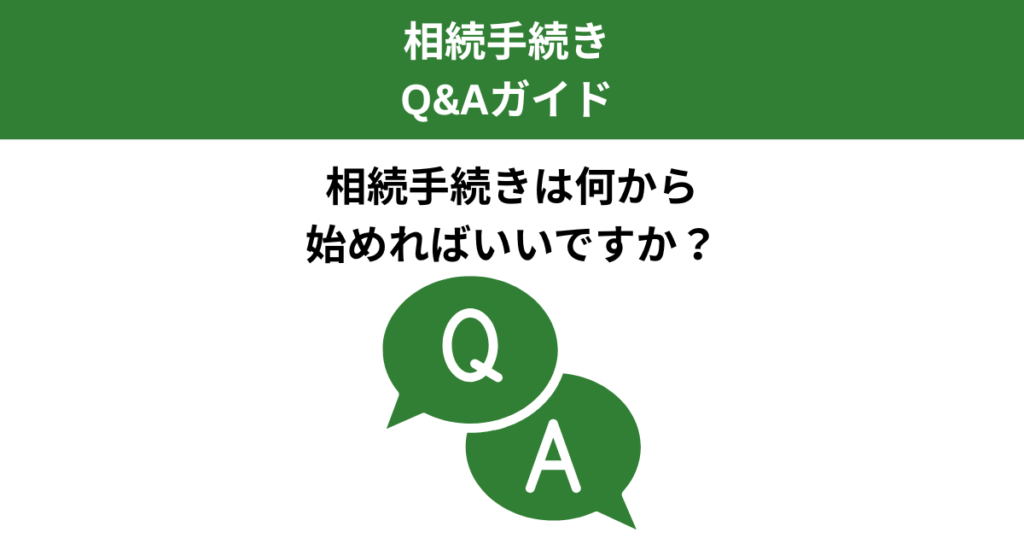
相続手続きは何から始めればいい?最初に確認すべきポイントと進め方の全体像
身近な方が亡くなったとき、突然始まる「相続手続き」。
慌ただしい中で「何から始めればいいのか分からない」と戸惑う方は多いものです。
特に、遺言書の有無や財産の内容によって進め方が大きく変わるため、最初の一歩を間違えると後の手続きに支障をきたすこともあります。
この記事では、「相続手続きは何から始めるべきか?」という疑問に対し、全体の流れと最初に確認すべき重要ポイントをわかりやすく解説します。
目次
相続手続きの最初のステップは「全体像の把握と情報収集」
相続手続きは、いきなり財産を分けるところから始めるのではなく、
まずは 「誰が相続人か」「どんな財産があるのか」「遺言があるか」 の3つを確認することからスタートします。
具体的には、次のステップで進めるのが一般的です。
-
死亡届の提出(7日以内)と火葬許可証の取得
-
遺言書の有無の確認(あれば家庭裁判所で検認)
-
相続人の確定(戸籍謄本の取り寄せ)
-
相続財産の調査(預金、不動産、借金など)
-
相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄)
-
遺産分割協議と協議書の作成
-
名義変更・解約手続き(預貯金・不動産など)
この流れの中で、特に最初の 「相続人・財産・遺言書の確認」 が重要です。
ここを飛ばしてしまうと、後の手続きがスムーズに進まなくなることがあります。
👉 関連記事:相続手続きの基本と落とし穴|家族が困らないために今すぐ知っておくべきこと
なぜ遺言書の確認が最初なのか?
相続手続きにおいて「遺言書があるかどうか」は、進め方を大きく左右します。
-
遺言書がある場合:原則として遺言の内容が優先され、遺産分割協議が不要になるケースもあります。
-
遺言書がない場合:法定相続人全員で協議し、遺産の分け方を決める必要があります。
また、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認手続き」 が必須です。
この手続きをせずに勝手に開封してしまうと、罰則(5万円以下の過料) の対象となることもあります。
👉 参考記事:自筆証書遺言とは?法改正後の保管制度と注意点を専門家が解説
相続人と財産の調査の重要性
「誰が相続人か」を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せる必要があります。
兄弟や前婚の子どもなど、思わぬ相続人が判明するケースもあり、慎重な確認が欠かせません。
一方で、「どんな財産があるか」についても漏れなく把握することが大切です。
-
銀行口座・証券・保険などの金融資産
-
不動産(固定資産税納付書や登記簿謄本で確認)
-
借金や保証債務などマイナスの財産
これらを確認せずに遺産分割を行ってしまうと、後から借金が見つかるなどトラブルに発展することがあります。
よくある誤解:「とりあえず口座を解約すればいい」は危険
「とりあえず故人の預金を解約してしまおう」と考える方もいますが、これは厳禁です。
相続人全員の合意がない状態での解約は「使い込み」と見なされ、トラブルの原因になります。
また、相続放棄を検討している人がいる場合、財産に手を付けることで 「単純承認(相続を承認したと見なされる)」 と判断されるリスクもあります。
そのため、口座や不動産などの名義変更は、相続人・遺言書・財産内容を整理した後に行うことが大切です。
行政書士や専門家のサポート内容
相続手続きは煩雑で専門知識を要するため、行政書士・司法書士など専門家のサポートを受けるのが安心です。
特に次のような場面で、専門家が力を発揮します。
-
戸籍収集や相続人調査の代行
-
遺産分割協議書の作成
-
預金・不動産などの名義変更サポート
また、相続税申告が必要な場合は、税理士と連携することでワンストップの対応が可能です。
👉 当事務所のサポート内容はこちら
相続手続きサポート|Kanade行政書士事務所(栃木県宇都宮市)
まとめ:まずは情報を整理し、専門家に相談を
相続手続きは、遺言書・相続人・財産の確認から始めるのが基本です。
焦って動くと、思わぬトラブルに発展することもあるため、まずは全体像を把握し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
相続は「家族の問題」でもあります。
信頼できる専門家とともに、安心して次の世代へつなぐための手続きを進めていきましょう。