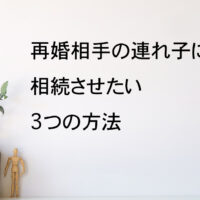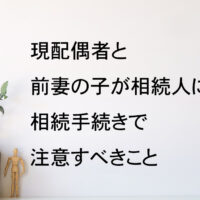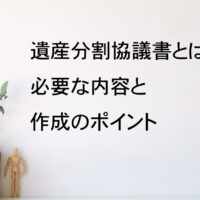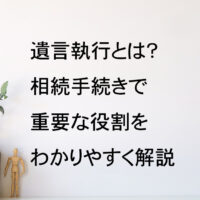コラム
2.32025
子どもなし相続第3回|配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース、宇都宮の相続手続きの注意点
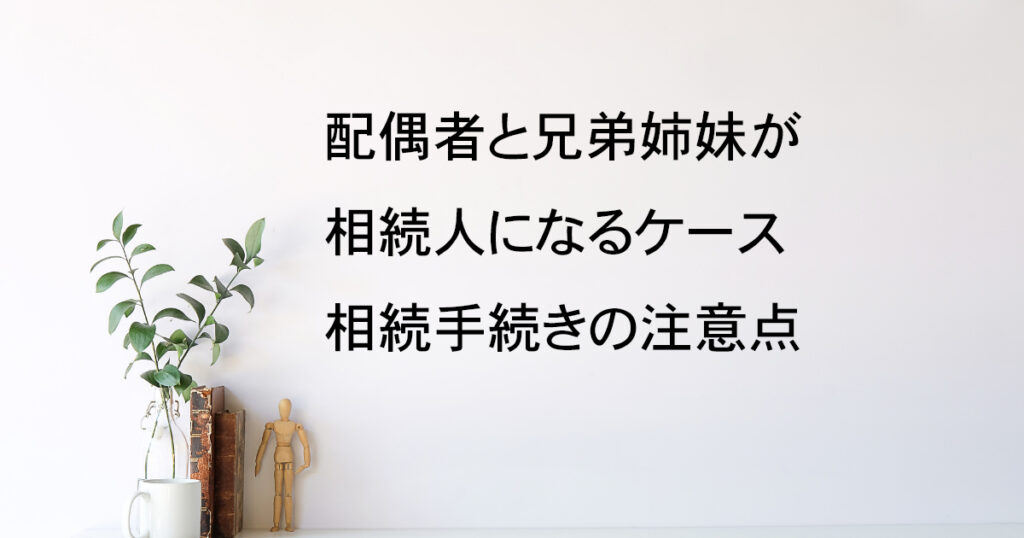
「子どもがいない相続」全5回シリーズ|第3回
栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。
今回は、「配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース」について、特に手続き上の注意点を中心にお伝えします。
相続人が「配偶者+兄弟姉妹」となるケースは、お子さんがいないご夫婦の相続で多く見られます。
このとき、「義理の家族との協議」が必要になるなど、他の相続とは異なるポイントがいくつかあります。
目次
配偶者と兄弟姉妹が相続人になるとは?
法定相続では、お子さんがいない場合、配偶者とともに被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
詳しい仕組みについては、こちらの記事でわかりやすく解説しています。
今回はその中でも、実際の手続きを進める際に注意すべき点についてお話します。
宇都宮で実際にあったご相談|事例から学ぶ
ケース①|相続の話を先延ばしにした結果、意見が対立…
「義理の兄に連絡するのが気まずくて、しばらく放っておいたら、
相手側から“全部でいくらあるんですか?”と急に詰められて困ってしまいました。」
このように、連絡を遅らせることで相手に不信感を与えてしまうケースがあります。
相続の話はデリケートですが、必要な情報は早めに整理しておくことがトラブル回避の第一歩になります。
ケース②|兄弟姉妹の一部が協議に応じてくれない…
「義理の妹が“私は関係ないから”と言って協議に参加してくれず、
他の兄弟と一緒にどうすればいいか悩んでいます。」
遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。
1人でも署名がもらえなければ手続きが進まないため、対応の順番や方法には注意が必要です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人のうち一人でも協議書への署名・押印を拒否すれば、他の手続きを進めることができず、相続全体が滞ってしまいます。
なぜ全員の合意が必要なのか?
相続財産は法的には共同相続人全員の共有状態にあるため、その分割には全員の同意が必須です。たとえば、預貯金の解約、不動産の名義変更などの手続きには、遺産分割協議書が必要となり、その書面には全相続人の署名・押印が求められます。
署名・押印を拒否された場合の対応
もしも相続人の一人が協議に応じない場合、まずはその理由を冷静に確認することが大切です。不満や誤解が原因であることも多く、丁寧な説明や再協議によって解決の糸口が見えることがあります。
それでも解決が難しい場合には、以下のような対応策があります。
・弁護士等の専門家を介入させ、客観的なアドバイスを受ける
・家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる
・調停不成立の場合には「審判」により裁判所が分割内容を決定
行政書士のサポート
行政書士は、遺産分割協議書の作成や、相続人調査などの面でサポートすることができます。協議が円滑に進むよう、中立的な立場から書類の整備や進行の補助を行い、必要に応じて他士業との連携も可能です。
このように相続は感情が絡むデリケートな問題でもあります。公平でスムーズな相続手続きを実現するためにも、早めの相談と準備をおすすめします。
手続き上の注意点はこの3つ
1.誰が相続人かを“早めに”確定すること
→ 被相続人の出生からの戸籍をしっかり確認。甥や姪が登場する場合もあります。
2.「感情」より「仕組み」を大事にすること
→ 法律で決まっていることを冷静に整理すると、無用な対立を避けられます。
3.手続き全体の“流れ”を把握してから動くこと
→ 名義変更や書類の手配など、見落としがちな作業が多いため、全体像をつかむことが大切です。
第2回でも触れた「子どもがいない相続の流れ」
配偶者として手続きを進める方の視点から知っておきたい基礎知識は、
▶️ 第2回|子どもがいない夫婦の相続手続き にて解説しています。
「どこから手を付ければいいのか分からない」という方におすすめです。
Kanade行政書士事務所でできるサポート

当事務所では、以下のようなサポートを行っています:
・相続人調査と戸籍の収集
・相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
・遺産分割協議書の作成支援
・名義変更などの流れの整理と書類案内
・他士業との連携によるワンストップ対応
特に、「配偶者と兄弟姉妹」という関係性ならではの気遣いを大切にしながら、できるだけスムーズに手続きを進められるようお手伝いしています。
最後に|ご不安な相続も、安心してご相談ください
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる相続は、手続きの複雑さだけでなく、人間関係のバランスにも気を配る場面が多いです。
Kanade(かなで)行政書士事務所では、宇都宮を中心に、こうした相続に関わる不安やお悩みに、丁寧に耳を傾けながら対応しています。
「話しにくい」「誰に相談していいか分からない」そのような状態のご相談でも大丈夫です。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム:こちらから