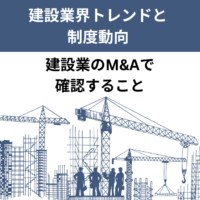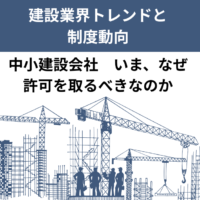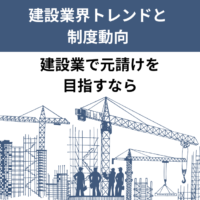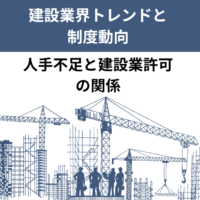- Home
- 建設業界トレンドと制度動向
- インボイス制度後の建設業界と許可取得の落とし穴とは【行政書士が解説】
コラム
11.242025
インボイス制度後の建設業界と許可取得の落とし穴とは【行政書士が解説】
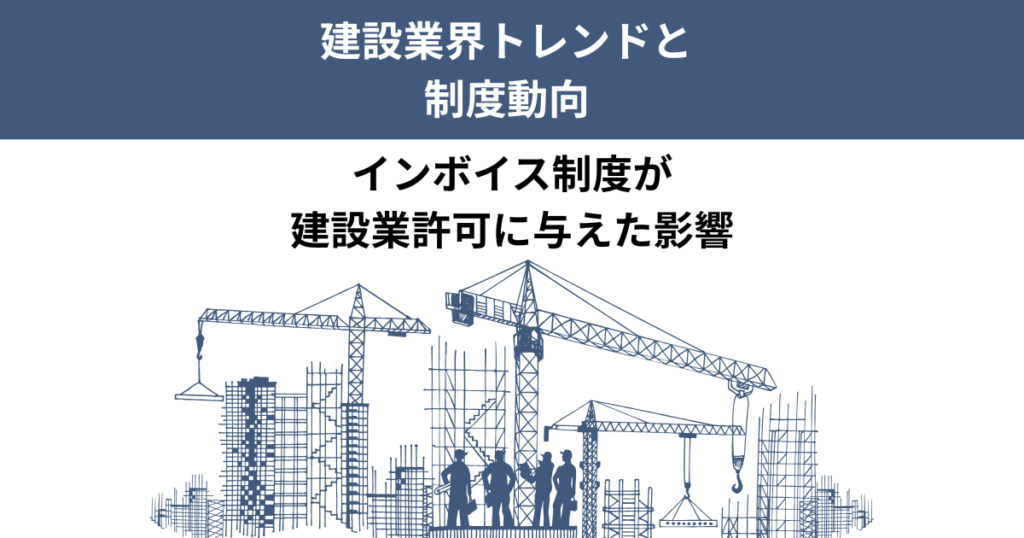
目次
インボイス制度後の建設業界と許可取得の落とし穴とは【行政書士が解説】
2023年10月にスタートしたインボイス制度は、建設業界にも大きな影響を与えています。特に、
- 個人事業主の一人親方
- 下請業者の多い工事会社
- 許可取得を検討している中小事業者
にとって、請求書の取り扱いや税務処理だけでなく、「建設業許可との関係」で見落とされがちなポイントが増えています。この記事では、インボイス制度が建設業に与えている影響と、許可取得・許可維持の場面で起きやすい“落とし穴”について、行政書士の視点から分かりやすく整理します。
1. インボイス制度が建設業界に与えた3つの変化
① 下請業者の選別が進み、実質的な「インボイス対応必須化」へ
建設業は多段階の下請構造が一般的で、元請は仕入税額控除のために「適格請求書」を必要とします。そのため実務では、
- インボイス非登録の業者に仕事を出しづらい
- 登録しない一人親方への仕事が出しづらい
- 法人化が急増する
こうした変化が顕著です。
② 免税事業者の“実質値下げ問題”が深刻化
免税事業者へ支払う工事代金から、元請は仕入税額控除ができません。そのため「消費税分の値引き交渉」が起きやすく、結果として免税事業者が不利になる構造が生まれてしまいがちです。
③ 法人化・許可取得の相談が急増
インボイス登録をきっかけに、
- 法人化(株式会社・合同会社)
- 建設業許可の取得
- 経管・技術者の体制整備
を考える個人事業主が増えています。しかし、この流れの中で許可取得の落とし穴 に気づかず失敗するケースも存在します。
2. インボイス制度後に増えた「建設業許可の落とし穴」
落とし穴①:法人化したのに、許可切替を忘れて“無許可状態”に
個人から法人に切り替える際に最も多いミスです。
▼ よくある事例
- 個人で許可 → 法人設立 → 法人の許可に切替していない
- 気づかず法人名で工事を受注し、無許可扱いに
許可は事業者ごと。個人と法人は全く別の主体のため、法人設立後は 許可の承継が必要 です。
落とし穴②:インボイス登録=許可要件が整ったと誤解する
インボイス登録は「税務上の登録」のみです。しかし中には、
「登録番号もあるし、もう“事業者としての信用”は問題ないですよね?」
と誤解されるケースがあります。
❌ インボイス登録= 建設業許可の要件(経管・技術者・財産要件)が整ったではありません。許可は、
- 経営管理責任者(経管)
- 営業所技術者等(専任技術者)
- 資本金や財務基準を満たす必要があります。
落とし穴③:一人親方(個人事業主)が急いで法人化 → 営業所技術者等(専任技術者)要件で止まる
インボイス登録のため法人化した一人親方が増えていますが、許可取得で最も多い壁が 営業所技術者等(専任技術者)の証明不足 です。
▼ よくある壁
- 資格はあるが、会社の技術者としての常勤性が証明できない
- 実務経験の証明書類(注文書・請負契約書)が揃わない
- 経管の経験が足りない
インボイス制度をきっかけに急ぎすぎて、「許可に必要な実務の積み上げ」が不十分なまま申請し、差し戻しになることがあります。
落とし穴④:消費税の負担増 → 経営事項審査(経審)で不利に
インボイス制度によって、下請への発注額や消費税負担が増えると工事利益率が下がり、経審の得点に影響する可能性があります。
- 工事利益が薄くなる
- 完成工事高に対し利益率が悪化
- 評点アップが難しい
結果として、公共工事の入札に影響が出ることがあります。
3. インボイス制度後に知っておきたい許可・経営のポイント
インボイス制度をきっかけに法人化を選ぶ建設業者が増えていますが、建設業許可は「いつ申請するか」で必要書類や要件が大きく変わるという点は意外と知られていません。ここでは、法人化のタイミング別に注意すべきポイントを整理します。
① 法人化するなら「許可取得のタイミング」を計画することが重要
建設業許可は、法人登記の前・直後・決算期までの期間、これらのどのタイミングで申請するかによって、必要書類・証明方法・審査の難易度が変わります。
▼ 法人登記の“前”に許可方針を決めるメリット
法人登記前に計画しておくと、許可に必要な体制を「整えながら」会社を作れます。
✔ 経営管理責任者(経管)を役員に入れられる
許可の必須要件である経管は、役員または経営業務を補佐する地位にある人である必要があります。
→ 登記前なら、経験年数のある人を役員に組み込んで設立できる。
✔ 営業所技術者等(専任技術者)を誰にするか調整できる
資格・経験のある人をあらかじめ社員・役員として迎えることが可能。
▼ 法人登記“直後”に申請する場合の注意点
設立直後は法人としての経歴がゼロのため、個人事業時代の実績をフル活用する形になります。
✔ 工事経歴は「個人時代」の資料を提出請負契約書
- 工事請負契約書
- 注文書及び工事請書
- 請求書等
など、個人事業の資料が大量に必要になるケースが多い。
✔ 経管・専任技術者の経験も個人時代で証明
法人設立の時点では実務経験がないため、すべて個人事業主としての経歴を使う。
✔ 財務証明は決算書ではなく「残高証明書」で代替
設立直後は決算書が存在しないため、創業時における財務諸表(開始貸借対照表)や500万円以上の残高証明で財務要件を証明する。
▼ 決算期までの期間に申請する場合
法人設立後半年〜1年で申請するケースです。
✔ 法人としての工事実績を使える場合がある
ある程度工事を行っていれば、法人名義の工事経歴で申請できる。(ただし、実績が足りなければ個人時代の資料を併用)
✔ 初決算前なら財務要件は「現預金」でOK
最初の決算前であれば、創業時における財務諸表(開始貸借対照表)や500万円以上の残高証明で財務要件を証明する。
▼ まとめ:同じ会社でも「申請時期」で書類も要件も変わる
- 登記前 → 体制を整えながら設立できる
- 登記直後 → 個人事業の資料が必須・残高証明で財務証明
- 決算期前 → 法人実績が活かせる場合あり
インボイス制度で法人化が増えていますが、許可申請まで逆算して会社設計をすることで、スムーズな申請が可能になります。
② 一人親方(個人事業主)は「経管経験」をどうつくるかが勝負
インボイス制度を機に法人化しても、経管の経験が足りず許可取得が1〜2年先になるケースが多いため、事前計画が必要です。
③ インボイス対応後の資金繰りに注意
- 消費税納付額が増える
- 仕入税額控除のための書類管理が増える
- 下請への支払いが増える場合あり
資金繰りは許可更新や経審にも直結します。
まとめ|インボイス制度後は、許可取得・維持で“見落としやすい点”が増えています
インボイス制度は建設業界に税務面だけでなく、許可・経営・人材確保の面でも影響を与えました。特に注意すべきは、
- 法人化と許可の切替
- 技術者要件・経管要件の不足
- インボイス後の利益率悪化
- 経審・資金繰りへの影響等
経営の体制が変わるタイミングは、専門家に一度相談することでリスクを大幅に減らすこともできます。