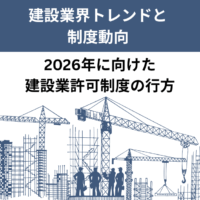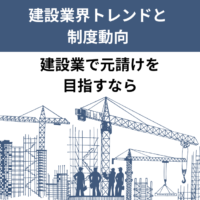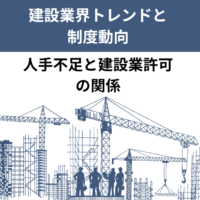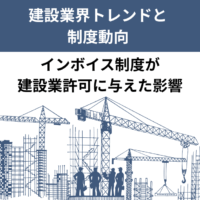- Home
- 建設業界トレンドと制度動向
- 2025年建設業法改正の最新動向|12月施行に向けた改正ポイントと実務準備
コラム
11.32025
2025年建設業法改正の最新動向|12月施行に向けた改正ポイントと実務準備
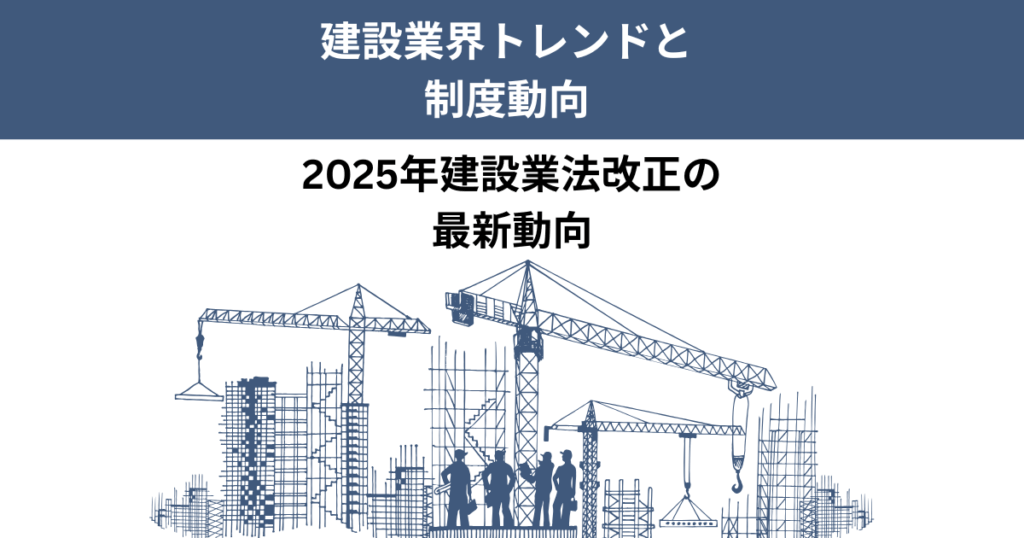
2025年、建設業界を取り巻く環境は大きな転換期を迎えようとしています。
人手不足や資材価格の高騰、働き方改革など、これまで積み上がってきた課題に対し、国は建設業法や関連制度の見直しを段階的に進めています。
本記事では、2025年12月からの制度施行を前に、現時点(11月)で公表されている内容を中心に、建設業許可に関わる改正ポイントと実務上の準備のヒントをまとめました。
「変化の前に、何を整えておくべきか?」という視点で、建設業者の経営者の皆さまに向けて、わかりやすくお伝えします。
建設業界が変わり始めた理由
この数年で、建設業界を取り巻く社会の変化は加速しています。
特に注目すべき3つの動きがあります。
-
人材不足の深刻化:若手の入職減少とベテラン層の引退が進行。
-
コスト構造の変化:資材価格や人件費の上昇による採算圧迫。
-
法制度の改正:担い手3法などの見直しで、取引の適正化と労務環境の改善が進む。
これらの流れを受け、行政の視点も「許可を取ること」から「持続的に守ること」へと重心が移っています。
いまや建設業許可は、企業の信頼性を測る“経営の指標”として位置づけられつつあります。
2025年12月施行予定の主な制度改正ポイント
1. 労務費の適正化と処遇改善
建設現場で働く人が安心して働ける環境を整えるため、**「著しく低い労務費での契約」や「不当な見積もり」**を防ぐ方向で制度整備が進行中です。
賃金水準や下請契約条件が、今後の許可審査や経営事項審査でもより注目される見込みです。
今のうちに見直すべきポイント
-
下請・協力会社との契約条件に労務費が正しく反映されているか。
-
自社の見積書・契約書テンプレートを最新の法令に合わせて更新する。
2. 資材高騰・工期ダンピング対策
資材価格や燃料費の変動を反映できるよう、契約変更のルール見直しが予定されています。
また、過度な短工期による「工期ダンピング」も防止対象とされ、品質・安全を担保する工期設定が重視されます。
今のうちにできる準備
-
契約時に「価格変動条項」を明示する仕組みづくり。
-
工期短縮が品質・安全に影響しないか社内でチェックする体制づくり。
3. 技術者配置とICT活用の推進
人材確保や現場効率化の観点から、ICT(情報通信技術)の活用がさらに広がります。
主任技術者・監理技術者の配置要件や、電子申請・デジタル台帳の導入が進むことで、紙書類中心の運用から脱却する動きが見られます。
現場対応のポイント
-
技術者情報・資格データをデジタル管理し、申請時の確認をスムーズに。
-
写真・報告書・工事記録をクラウドで整理し、証拠書類の整備負担を軽減する。
経営者が今、確認しておきたいチェックリスト
2025年12月施行を前に、次の5点は早めに点検しておきましょう。
✅ 現在の許可業種・区分(一般/特定)を正確に把握しているか
✅ 専任技術者・常勤役員の要件を満たしているか
✅ 労務費・資材費の見積もり根拠を明示できるか
✅ 下請契約書や注文書が最新の制度に対応しているか
✅ 書類・証憑を電子データで管理できる体制が整っているか
この5項目を整えるだけでも、制度改正後のトラブルや再申請リスクを大幅に減らすことができます。
行政書士として感じる「これからの建設業許可」
建設業許可は、かつてのような“書類上の許可”から、「働く人を守り、取引の公正を保つための基盤」へと役割を変えつつあります。
制度改正のたびに「手続きが増える」と感じる方も多いと思います。
しかし、その変化の本質は、企業の信頼と経営品質を高める仕組みにあります。
日々、現場で奮闘される経営者の方々が、制度を“守るためのルール”ではなく“成長の道しるべ”として活かせるよう、私も行政書士として丁寧に伴走していきたいと感じています。
まとめ
2025年の制度改正は、単なる法令変更ではなく、「人」「取引」「経営」を支える仕組みへと進化するものです。
本格施行(2025年12月)を前に、今のうちから準備を進めることで、余裕を持って対応することができます。
小さな見直しが、次の一歩につながります。
この記事が、現場を支える皆さまの判断と行動のヒントになれば幸いです。

2026年に向けた建設業許可制度の行方|行政書士が見据える次の改正と業界の未来