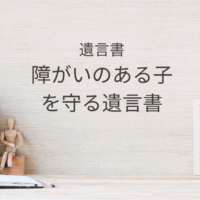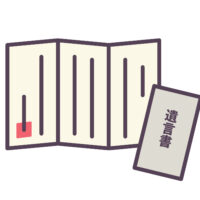コラム
1.212025
第7回|宇都宮の事例から学ぶ!もめた遺言・もめなかった遺言の違いとは?
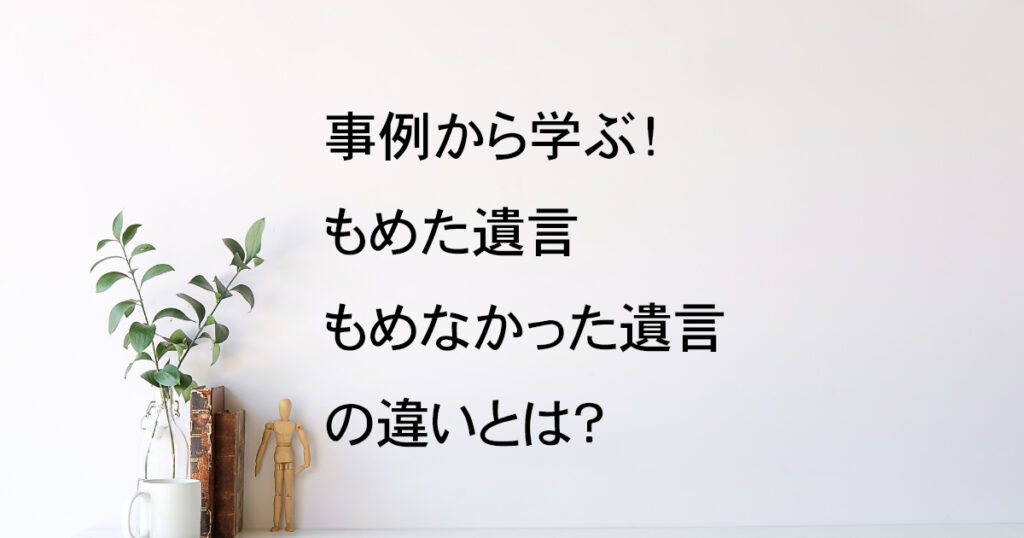
栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所です。相続に関するご相談をお受けする中で、「遺言書があったのに、結局トラブルになってしまった。」という一方で、「遺言がきちんと用意されていたおかげで、スムーズに手続きを進められた。」というお話を伺います。
なぜ、遺言書が準備されていたのに、結果として「もめてしまう」ケースと、「穏やかに進む」ケースがあるのでしょうか?その違いは、単に「遺言があるかどうか」だけではなく、どのように書かれていたか、どれだけ配慮があったかなどによって大きく分かれてくるのです。今回は、栃木県宇都宮市内のご相談より、実際の事例をもとに、「もめた遺言」と「もめなかった遺言」の違いについて、行政書士の視点からお伝えします。
目次
「遺言書さえあれば安心」は、本当?
遺言書があると、相続手続きがスムーズに進むと思われがちです。もちろん、遺言があること自体はとても重要なのですが、内容が偏っていたり、法律上の形式が整っていなかったり相続人全員への配慮がまったくなかったりするとむしろトラブルの“火種”になることもあるのです。逆に、しっかりと想いと法的な配慮を込めて作られた遺言は、「これでよかったんだ」と遺された方々の気持ちを落ち着かせてくれる効果があるように感じます。
【宇都宮の事例①】兄弟で揉めた遺言|原因は「説明不足」
宇都宮市内でのご相談事例です。
Aさんは兄弟2人のうち、長男に全財産を遺すという内容の自筆証書遺言を残して亡くなりました。遺言には「すべて長男に相続させる」とだけ書かれており、次男には一言も触れられていませんでした。結果、次男は納得できず、「兄ばかりに全部相続させるのは不公平だ。」として遺留分の請求を起こしました。遺言の効力そのものは有効でしたが、兄弟の仲はすっかりこじれてしまい、その後の関係にも大きな溝が残ってしまったそうです。実際には、長男が親の介護を長年担ってきた背景がありましたが、それを次男は知らなかったため、余計に誤解が広がってしまったのです。
「何も話してくれなかった。」「なぜ自分には一言もなかったのか。」といった、遺言の内容そのものよりも、“気持ちの部分”が整理されていなかったことが、トラブルのきっかけになってしまったのかもしれません。
【宇都宮の事例②】家族円満で進んだ遺言|想いが伝わった付言事項
一方で、別のBさんは、公正証書遺言を作成されていました。財産の多くを長女に相続させるという内容でしたが、遺言書の末尾にこんな付言事項が添えられていました。
「これまでずっと介護してくれた長女に感謝しています。他の子どもたちもそれぞれの家庭で頑張っていることは分かっています。どうかお互いに感謝と尊重の気持ちを持って、仲良く過ごしてくれたら嬉しいです。」
この一文があったおかげで、他のご兄弟は「お父さんの気持ちがわかった」と納得され、相続は円満に進みました。法的効力はない「付言事項」ですが、心をつなぐメッセージとしての力はとても大きいと感じた事例でした。
もめない遺言にするための3つのポイント
では、どうすれば「もめない遺言」に近づけることができるのでしょうか?行政書士として、次のような点を大切にしています。
① 法的に有効な形式で書くこと
自筆証書遺言は法的要件を満たしていないと無効になることも。確実性を求めるなら、専門家のアドバイスを求めることや公正証書遺言がおすすめです。
② 財産と相続人の全体像を把握すること
「誰に何を遺すか」の前に、財産の一覧や相続人の構成を整理することも重要です。
③ 付言事項で気持ちを添えること
相続人の間に差をつける場合は、その理由や背景を伝える言葉があるだけで、受け取り方が全く違ってくる場合もあります。
宇都宮で遺言作成を検討中の方へ
遺言書は、「法的な書類」であると同時に、大切な人への最後のメッセージでもあります。どんなに内容が正しくても、思いやりが伝わらなければ、トラブルの火種になってしまうことも。
逆に、しっかり準備された遺言は、ご家族の「これから」を優しく後押ししてくれます。
ご相談はお気軽にどうぞ(初回無料)
栃木県宇都宮市のKanade(かなで)行政書士事務所では、形式だけでなく「想いが伝わる遺言書」を大切に、丁寧にサポートしております。
・家族で揉めないようにしたい方
・感謝の気持ちをきちんと残したい方
・ご高齢の方やそのご家族
初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
▶関連記事