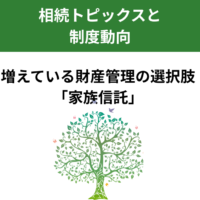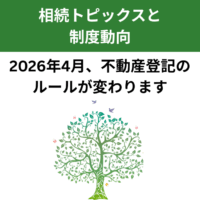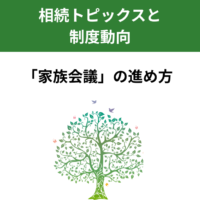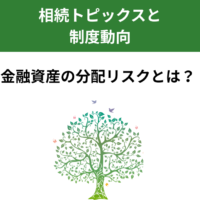- Home
- 相続トピックスと制度動向
- 親の認知症と相続で悩まないために|任意後見契約という選択肢
コラム
11.172025
親の認知症と相続で悩まないために|任意後見契約という選択肢
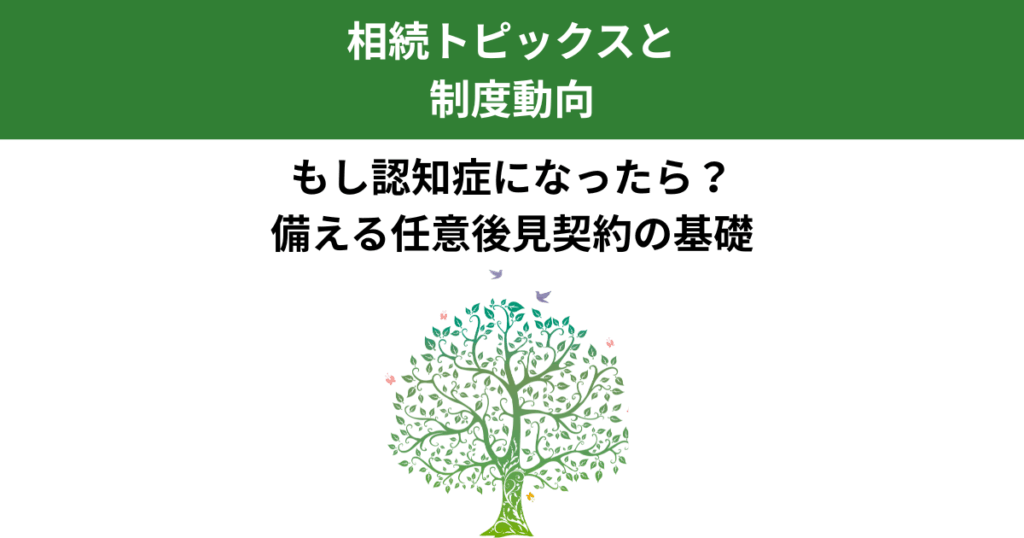
目次
親の認知症と相続で悩まないために|任意後見契約という選択肢
高齢化が進むなか、認知症と相続の問題は年々深刻さを増しています。特に注目されているのが、**「認知症によって相続手続きが止まってしまうケースの増加」**です。
認知症が進行すると、財産管理や相続対策が本人では行えなくなり、家族も手続きを進められなくなることから、早期の備えへの関心が高まっています。この記事では、認知症と相続の関係、そして本人が元気なうちに準備できる 任意後見契約 のポイントをわかりやすく整理し、これからの備え方を紹介します。
認知症が相続手続きに与える影響
認知症が進行し、本人の判断能力が不十分になると、次のような相続関連の手続きが進められなくなることがあります。
-
遺言書をつくる
-
不動産を売却・管理する
-
預貯金の管理や支払いを行う
-
相続人との話し合いに参加する
相続は「本人の意思」が前提となる部分が多いため、認知症によって手続きが止まるケースは全国的に増えています。
認知症のリスクが高まる中で、相続と財産管理の両方をどのように備えるかが重要なテーマになっています。
任意後見契約とは?(制度の基本)
任意後見契約とは、本人が判断能力のあるうちに、将来の財産管理を誰に任せるのかを決めておく制度です。
契約内容は公正証書で作成し、本人の判断能力が低下した段階で後見人のサポートが開始されます。
任意後見契約のポイントは次のとおりです。
-
本人が元気なうちに契約できる
-
信頼できる家族や知人を後見人として指定できる
-
判断能力が衰えた後でも財産管理を継続できる
-
施設入居や生活費の管理も円滑になる
🔗 参考:法務省「成年後見制度 成年後見登記制度について」(PDF)
法定後見との違い(2024年以降の相談で増えているポイント)
任意後見とよく比較されるのが 法定後見制度 です。
| 制度 | 利用のタイミング | 後見人の決定方法 | 本人の意思反映 |
|---|---|---|---|
| 任意後見 | 判断能力があるうちに準備 | 本人が選ぶ | 反映されやすい |
| 法定後見 | 判断能力が低下してから申立て | 家庭裁判所が選ぶ | 希望が通らないことも |
相続手続きや財産管理の現場では、「認知症が進んでからでは選べない」という理由から、任意後見契約への関心が大きく高まっています。
なぜ今、任意後見契約が注目されているのか(社会背景)
任意後見契約が注目される背景には、以下のような事情があります。
-
認知症高齢者の増加
-
相続手続きの複雑化
-
不動産管理の必要性が増している
-
家族のライフスタイルが多様化し、近居・別居が増えている
特に不動産については、相続登記義務化にも関連し、本人の判断能力がないと名義変更が進められないため、より早い段階での備えが求められるようになっています。
任意後見契約を利用するときの一般的な注意点
任意後見契約は便利な制度ですが、次のような点には注意が必要です。
-
後見開始には家庭裁判所の手続きが必要
-
後見監督人の選任(監督人報酬)が発生する
-
契約内容を明確にしておかないと誤解が生まれる
-
すぐには効力が発生せず、判断能力低下後に開始
制度の仕組みや限界を理解したうえで利用することが大切です。
制度の目的 ― 認知症による“手続き停止”を防ぐため
任意後見制度の目的は、認知症などにより財産管理が困難になった場合でも、本人の意思に沿った管理を継続することです。
認知症による「相続手続きの停止」や「財産の凍結」を防ぎ、家族の負担やトラブルを未然に減らす役割があります。
実務での役割分担(一例)
-
行政書士:相続関係の整理、財産情報の整理、任意後見契約の前段階の相談支援
-
司法書士:任意後見契約の登記、後見申立て、財産管理(後見人)
-
弁護士:紛争性を含む案件の対応
任意後見契約は、多くの場合複数の専門家が関わる制度です。
まとめ
認知症と相続をめぐる問題は、これからさらに増えていくと予想されています。
任意後見契約は「元気なうちにできる相続準備」として注目されており、
-
財産管理の継続
-
相続手続きの停止を防ぐ
-
家族の負担軽減
-
本人の意思を尊重できる
というメリットがあります。
認知症のリスクが高まる現代では、早めの準備こそが安心への第一歩です。