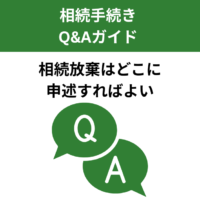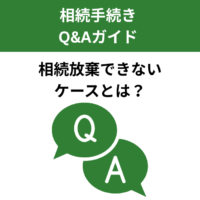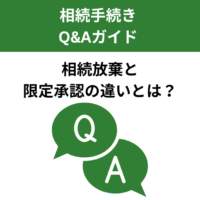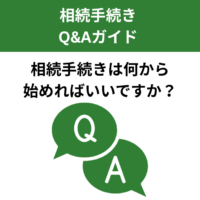- Home
- 相続手続きQ&Aガイド
- 遺言書がある場合でも遺産分割協議は必要ですか?
コラム
11.72025
遺言書がある場合でも遺産分割協議は必要ですか?
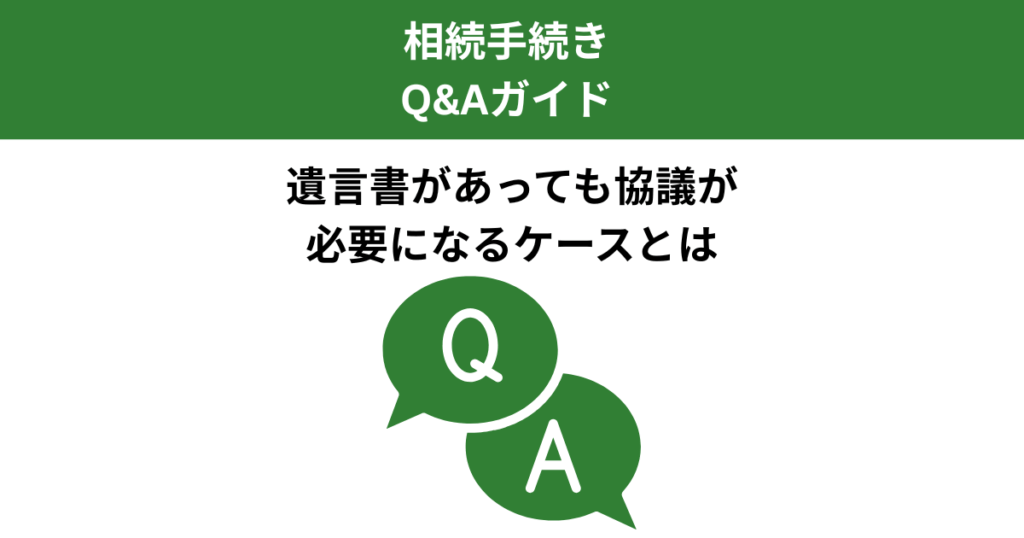
目次
遺言書がある場合でも遺産分割協議は必要ですか?
A. 原則、不要です。
遺言書の内容に従って分割されるため、原則は不要となります。ただし、例外的に遺産分割協議が必要になるケースもあります。
遺言書がある場合の基本的な考え方
有効な遺言書があるときは、その内容が法的に優先されます。
つまり、相続人同士で「誰が何を相続するか」を改めて話し合う必要は基本的にありません。
たとえば、
「不動産は長男に相続させる」「預金は妻に相続させる」
といった内容が明確に書かれていれば、その通りに相続の手続きを進めます。
遺産分割協議が「必要になる」3つのケース
一方で、遺言書があっても協議が必要となる場合があります。
代表的なのは次の3つです。
-
遺言書に書かれていない財産があった場合
→ 例えば、不動産や預金が一部漏れている場合は、残りの財産について相続人全員で分け方を話し合う必要があります。 -
遺言の内容があいまいな場合
→ 「預金の一部」や「土地の半分」といった表現だと、具体的に誰がどれを取得するか不明確なため、協議で確認することになります。 -
相続人全員が遺言の内容に同意して変更したい場合
→ たとえば、実際の生活状況に合わせて遺言の内容を柔軟に変えたいときは、全員の合意があれば協議書を作成して調整することも可能です。
注意点 ― 遺言の「有効性」を確認してから進めましょう
自筆証書遺言の場合、内容が法的に有効かどうか(方式に不備がないか)を確認することが重要です。
特に日付・署名・押印の欠落などがあると、無効と判断されるおそれがあります。
相続人間で争いを避けるためにも、手続きを進める前に、遺言書の有効性や保管状況(法務局保管かどうか)を確認しておくと安心です。
専門家に相談するメリット
遺言書がある場合でも、実際の手続きでは「遺言に含まれていない財産」や「登記・解約などの関連手続き」が必要になることがあります。
行政書士は、
-
相続関係説明図の作成や戸籍収集など、遺言内容を実現するための前提整理
-
遺言執行に向けた準備や、関係者間の情報整理
-
他士業(司法書士・税理士など)へのスムーズな引き継ぎ支援
といった形で、遺言書の内容が円滑に実現されるための流れを整えるサポートを行うことができます。
遺言を「作る段階」だけでなく、「実際に動かす段階」でも、全体を見渡して整理しておくことが、家族にとっての安心につながります。
まとめ ― 遺言があっても「確認と整理」が大切
遺言書があれば相続手続きはスムーズに進むことが多いですが、その内容を正確に理解し、抜けや重複がないかを確認しておくことが大切です。
「遺言がある=話し合いは不要」ではなく、家族が納得して進められるように整理することが、結果的にトラブルを防ぐ一番の近道です。