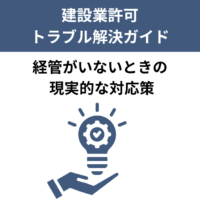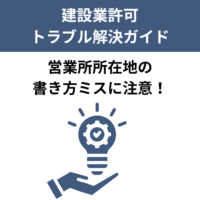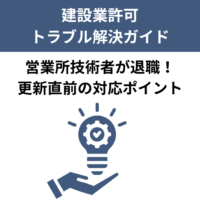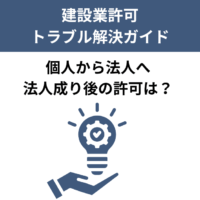- Home
- 建設業許可トラブル解決ガイド
- 建設業許可が下りない理由とは?代表者の経歴要件でつまずいた事例と対策
コラム
11.62025
建設業許可が下りない理由とは?代表者の経歴要件でつまずいた事例と対策
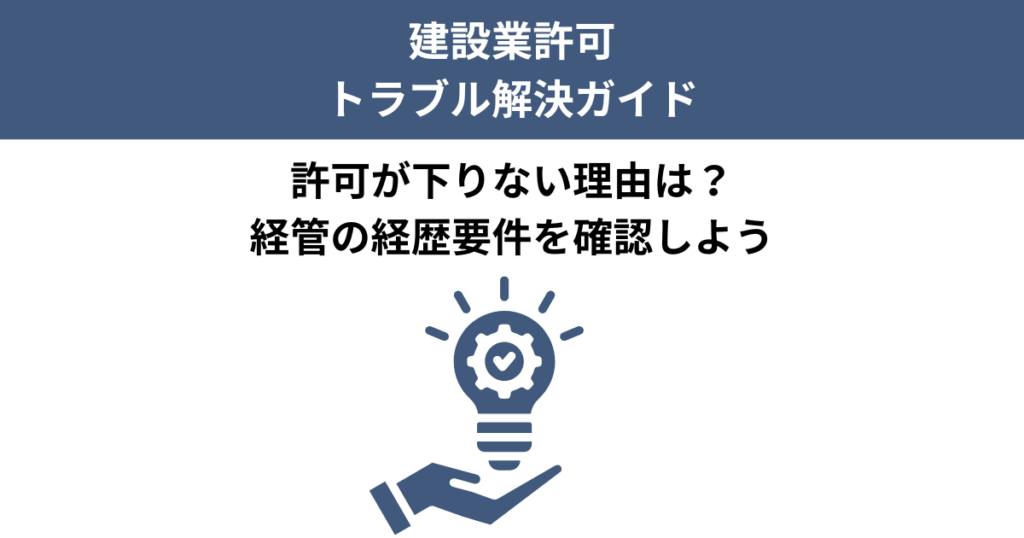
「建設業許可が下りなかった」と聞くと、多くの方が「書類の不備があったのかな」と考えがちです。
しかし実際には、代表者(経営業務の管理責任者)としての「経歴要件」を満たしていなかったことが原因となるケースが少なくありません。
この記事では、申請時に見落とされがちな代表者要件のポイントと、許可取得に向けた改善策をわかりやすく解説します。
目次
経営業務管理責任者とは?(2025年時点)
建設業許可を取得するには、営業所ごとに経営業務管理責任者(以下、経管)を置くことが必要です。
経管は、会社や個人事業主として経営業務を総合的に管理した経験を持つ人物であることが求められます。
主な要件(一般建設業の場合)
-
法人の場合:常勤の役員として、過去5年以上建設業の経営に関与していた経験
-
個人事業の場合:5年以上、自ら建設業を営んでいた経験
-
準ずる地位(支店長・工事部長など)として、一定の実績を有する場合も可
ただし、単なる従業員や現場監督としての勤務年数だけでは「経営業務の管理経験」として認められない点に注意が必要です。
よくある不許可事例 ― 経歴証明のつまずき
事例① 前職での役職証明が取れなかった
ある建設会社の代表が、自身の前職を「建設業における部長職」として申請しました。
しかし、退職した会社がすでに解散しており、役職を証明する書類(在職証明・登記事項証明等)を提出できなかったため、要件を満たさないと判断されました。
👉 対策
在職証明書が得られない場合は、工事契約書・請求書・確定申告書など複数資料を組み合わせなどて実務関与を示すなどもあります。不明な場合は、許可行政庁に確認しましょう。
事例② 親族会社での関与を誤認して申請
家族経営の会社で「役員のような立場で関与していた」として申請したところ、実際の登記上の役員登記はされておらず、形式的には経営業務に関与していないと判断されました。
👉 対策
登記簿上の役員登記や職務内容を明確にしておくことが重要です。
近年は「実質的な経営関与」の判断も柔軟化していますが、裏付け資料の整備が不可欠です。
改正動向 ―「経管の要件緩和」と今後の注意点
2020年の法改正で、経営業務管理責任者の専任要件は一部緩和され、組織内に複数の経験者がいる場合、経営を補佐できる体制があれば認められるようになりました。
しかし、形式的に「補佐できる」と記載しても、
-
実際の職務分担
-
社内決裁の流れ
-
事業実態の継続性
が確認する資料の提出が必要となります。添付資料がきちんと整っているか確認が必須です。
経歴要件で不安を感じたら確認したい3つのチェックポイント
-
登記簿・履歴事項証明書の役職内容が最新か
-
経営業務の内容を説明できる資料(契約・請求・発注履歴など)があるか
-
建設業における経営判断や責任を担っていたことが示せる資料は整っているか
これらをあらかじめ整理しておくと、申請前の補正や面談でスムーズに対応できます。
専門家の立場から ― 書類の前に「整理」が必要な理由
経歴要件でつまずく多くのケースは、「書類がない」というより、「経歴の整理が曖昧」なことにあります。
まずは「どの期間」「どの立場で」「何を決めていたか」を時系列で明確にするだけでも、揃えるべき資料が明確になることもあります。
書類作成の前に、まずは自社の履歴・登記・業務内容を丁寧に見直すこと。
それが、確実な許可取得への第一歩です。
まとめ
代表者の経歴要件は、建設業許可の中でも特に慎重に確認される項目です。肩書きや在籍年数だけでなく、その人が実際にどのように経営業務に関わってきたか、という「実態」が見られます。