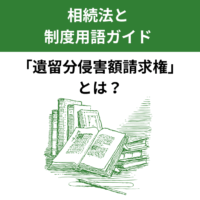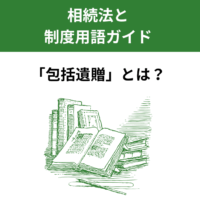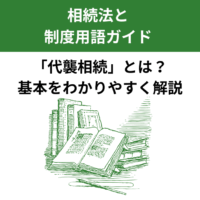- Home
- 未分類, 相続法と制度用語ガイド
- 「相続回復請求権」とは?時効と行使方法をわかりやすく解説
コラム
11.52025
「相続回復請求権」とは?時効と行使方法をわかりやすく解説
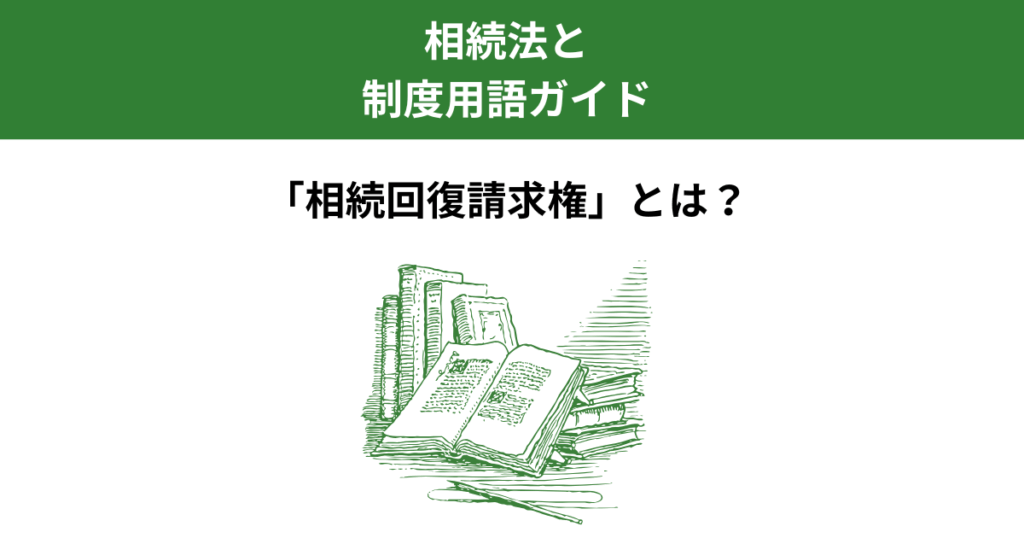
「相続回復請求権」という言葉を耳にしたことはありますか?
これは、本来の相続人が相続権を侵害されたときに、その権利を取り戻すための請求権です。
たとえば、他の相続人が自分を除外して遺産をすべて取得してしまった場合や、自分の相続分を無視して登記を進めてしまったようなケースが該当します。
この記事では、相続回復請求権の基本的な考え方と、知っておきたい時効・手続きのポイントをわかりやすく整理します。
相続回復請求権とは
相続回復請求権は、民法884条に定められている制度で、「相続権を侵害された者が、相続権を回復するために行使できる権利」とされています。
この制度が想定しているのは、次のような場面です。
-
本来の相続人ではない人(例:誤認された養子など)が遺産を取得してしまった
-
他の相続人が、相続分を超えて不動産などを単独で登記した
-
自分の相続分がまったく考慮されず、遺産分割が進められてしまった
つまり、「自分にあるはずの相続権が、誰かの行動によって失われた」ときに、正当な権利を回復するための法的手段が相続回復請求権です。
相続回復請求権の時効
相続回復請求権には、行使できる期間(時効)が定められています。
民法884条では、次の2つの期間のいずれか早い方が適用されます。
-
相続権を侵害されたことを知ったときから5年
-
相続開始のときから20年
このため、「知らなかった」としても、相続開始から20年が経過すると請求できなくなる可能性があります。
また、具体的な時効の起算点(いつから数えるか)は個別の事情によって異なるため、早めの確認と準備が大切です。
相続回復請求と他の手続きとの違い
相続回復請求権と似た言葉に「遺産分割のやり直し」や「登記の訂正」がありますが、それぞれ目的が異なります。
| 手続き名 | 主な目的 | 主な利用場面 |
|---|---|---|
| 相続回復請求 | 相続権を侵害されたときに、権利そのものを回復する | 相続人としての地位を無視された場合など |
| 遺産分割のやり直し | 合意内容を変更する | 後から新たな遺産が見つかった場合など |
| 登記の訂正 | 登記内容を正す | 相続登記で誤記や漏れがあった場合など |
相続回復請求は「自分が相続人である」という立場を取り戻すための権利であり、他の相続手続きよりも根本的な権利関係の回復を目的としています。
相続回復請求を考えるときの注意点
-
早めに権利侵害の有無を確認する
相続開始後、遺産分割や登記の流れを見落とすと、気づかないうちに時効が進むことがあります。 -
証拠となる資料を整理しておく
戸籍や登記簿、遺産分割協議書の写しなど、権利を確認できる資料を早めに整えましょう。 -
話し合いで解決できる余地を探る
まずは関係者間で事実確認を行い、誤解や認識違いを整理することも重要です。
専門家の立ち会いで冷静に確認することで、円満解決につながるケースもあります。
行政書士がサポートできる範囲
相続回復請求権の具体的な行使(訴訟・裁判)は弁護士の領域にあたりますが、行政書士としては、相続に関わる状況や情報を整理し、話し合いの土台を整えるサポートを行います。また、必要に応じて関係士業へ適切におつなぎし、円滑な対応が進められるよう支援します。
相続トラブルの背景には、感情面のすれ違いや「知らなかった」ことによる誤解が多く見られます。
全体の流れを整理し、今後の手続きを見通すことで、冷静に判断しやすくなります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。
具体的な権利関係の争いが想定される場合や、訴訟・登記などの手続きが必要な場合は、それぞれの専門職(弁護士・司法書士など)へご相談ください。
まとめ ― 相続権を守るためにできること
相続回復請求権は、相続権を侵害されたときに正当な権利を取り戻すための制度です。
ただし、時効の制限があるため、早めの確認と情報整理が重要になります。
まずは、家族関係や相続人の範囲を正確に把握し、権利関係に疑問を感じたときは、専門家へ相談してみることをおすすめします。
権利を守るための一歩は、冷静に状況を整理することから始まります。
【補足メモ】(2025年11月時点)
本記事の内容は、2025年11月時点の民法および相続関連制度に基づいています。
法改正や判例動向により運用が変わる可能性があるため、最新情報の確認をおすすめします。