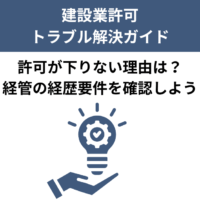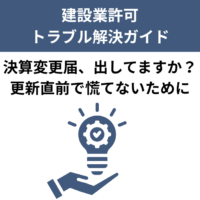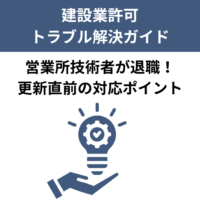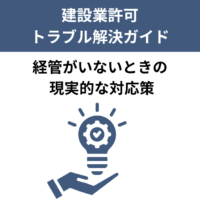- Home
- 建設業許可トラブル解決ガイド
- 法人化してから建設業許可の切替を忘れていた手続きトラブル
コラム
10.302025
法人化してから建設業許可の切替を忘れていた手続きトラブル
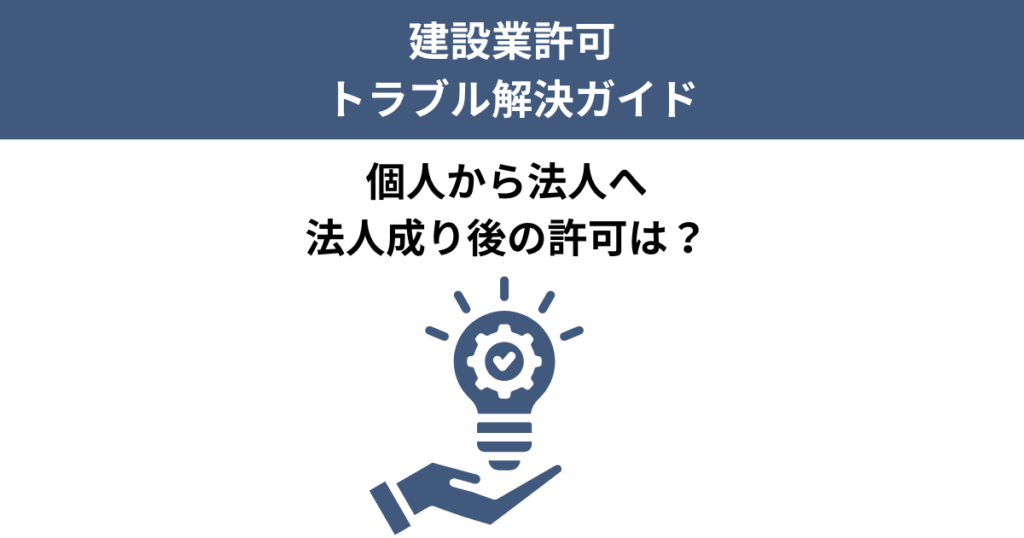
法人化してから建設業許可の切替を忘れていた手続きトラブル
(許可の承継制度〈事前認可〉との違いも解説)
目次
うっかり見落としがちな「法人化後の許可」
個人から法人へ「法人成り」した後、建設業許可をそのまま使えると誤解してしまい、法人名義の新規許可や承継の手続きを失念するケースは少なくありません。建設業許可は事業者(主体)ごとの許可であり、個人と法人は別主体です。したがって、原則は「個人=個人の許可」「法人=法人の許可」として扱われます。
ただし、令和2年10月の法改正により、一定の要件の下で事前に認可を受ければ「建設業者としての地位」を承継できる制度が創設されました。これにより、従前のような「廃業→新規許可までの空白期間」を発生させずに、許可を引き継げる道が開かれています。
ケース:指摘されて判明することが多い
法人化後、見積・契約を法人名で進めていたところ、発注者から「許可番号が個人名義のまま」と指摘され発覚。この場合
-
承継の事前認可を経ていなければ、新規で法人許可を取り直す必要が生じる
-
入札・契約や取引審査で不備扱いになり得る
-
一定の場合に「無許可」リスクが顕在化する
といった影響が出ます。
令和2年改正のポイント(事前認可で「地位」を承継)
-
制度の趣旨:事業譲渡・合併・分割、相続の局面で、事前認可(相続は死亡後30日以内)を受けることで、「建設業者としての地位」を承継できる。空白期間なく事業継続が可能。
-
対象行為:事業譲渡・合併・分割(=事業承継)および相続。個人→法人の法人成りも、実質的に事業譲渡等として承継制度の射程に入る形で運用される(全部承継が前提)。
-
全部承継が原則:許可業種の一部のみの承継は不可。一部承継をしたい場合は、承継元で当該許可を廃業し、承継先が新規許可を受ける必要がある。
-
要件:承継先が承継後に有する全業種で「許可要件(営業所技術者等、経営体制、社会保険等)」を満たすこと。
「承継(事前認可)」と「新規許可(切替)」の違い
| 比較項目 | 承継(事前認可あり) | 新規許可(切替) |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 建設業法17条の2・3(令和2年改正) | 建設業法3条(主体変更に伴う新規) |
| 手続き時期 | 承継の事実が生じる前に認可申請(相続は死亡後30日以内) | 旧主体を廃業→新主体で申請 |
| 許可の連続性 | 原則連続(空白期間なし) | 申請~許可まで空白が生じ得る |
| 承継の範囲 | 「地位」丸ごと承継(全部承継) | 新主体で一から要件審査 |
| 監督処分・経審 | 承継する(下段参照) | 新主体としてゼロから |
出典:制度概要・運用要件(国交省)
重要:監督処分・経営事項審査(経審)の結果も承継
「地位」を承継するということは、単に“許可番号”だけでなく、権利義務の総体を引き継ぐことを意味します。したがって、被承継人が受けた監督処分や経営事項審査の結果は、承継人に当然に承継されます(罰則の「刑」は承継されない旨の整理あり)。
さらに、監督処分の運用基準でも、承継人に対する処分の考え方が明記されています。承継後のコンプライアンス体制の整備は必須です。
実務の勘所(法人成りを想定した最小チェックリスト)
-
承継スキームの選定:法人成りが「事業譲渡等」に当たる設計かを確認(全部承継が前提)。
-
事前認可の申請タイミング:承継の効力発生日前に認可申請(相続は死亡後30日以内)。
-
要件の充足:承継後の全業種で、営業所技術者等・社会保険・経管要件等を満たす体制に。
-
経審・処分の引継ぎ意識:経審点や過去の処分影響が承継後にも及ぶことを前提に、体制改善をセットで。
まとめ
-
令和2年改正で、事前認可により「建設業者としての地位」を承継できるようになりました。空白期間を回避できます。
-
個人→法人の法人成りでも、スキーム設計と要件充足、事前認可が整えば承継の対象たり得ます(ただし全部承継が原則)。
-
承継は“良い面だけ”を引き継ぐ制度ではありません。監督処分や経審の結果も承継されます。承継後のガバナンス強化が不可欠です。
*出典参考:
国土交通省(建設業者の地位の承継について
国土交通省(国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について)
国土交通省関東地方整備局(事業承継等の事前認可制度)