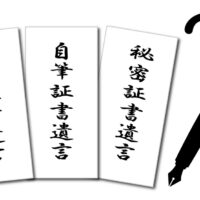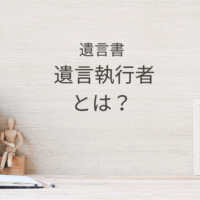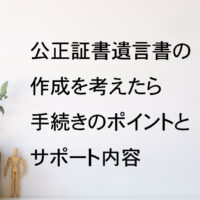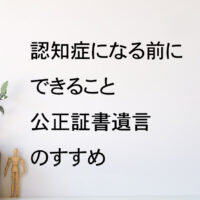コラム
5.142025
養子縁組している場合の遺言書|実子・養子の相続関係と注意点を整理
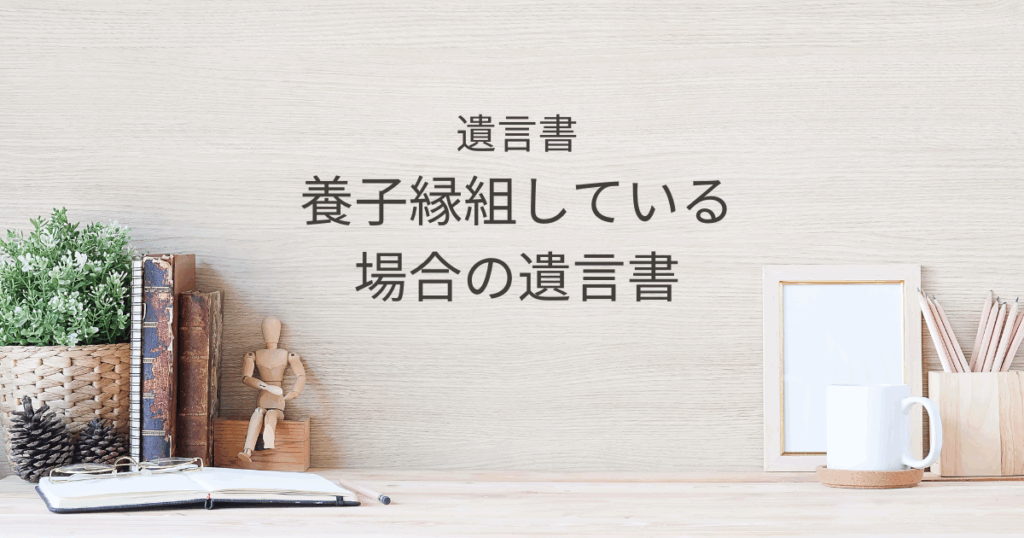
目次
養子縁組している場合の遺言書|実子・養子の相続関係と注意点を整理
養子縁組をした家族にとって、遺言書はとても大切な意味を持ちます。
実子と養子の相続権は基本的に平等ですが、感情や事情が絡むことで、思わぬトラブルにつながることも少なくありません。
「うちには養子も実子もいるけれど、分け方はどうすればいいの?」
「特別養子縁組だと何が違うの?」
「不公平感をなくしたいが、どう記載するのが良い?」
こうした疑問や不安を解消できるよう、この記事では養子縁組をしている場合の遺言書のポイントや注意点をわかりやすく解説します。
養子と実子の相続権は同じ?法律上の基本
養子縁組をすると、その子は「法律上の子ども」として扱われます。
遺言書を作らなかった場合、法定相続分は実子と同じです。
普通養子縁組の場合
普通養子縁組は、実親との親子関係を維持したまま養親の子になります。
そのため、実親が亡くなった場合も法定相続人となります。
例:
-
Aさん(養親)が亡くなる→養子はAさんの子として相続
-
実親Bさんが亡くなる→養子はBさんの子としても相続
つまり、二重の相続権が認められています。
特別養子縁組の場合
特別養子縁組は、実親との親子関係が消滅し、養親の子としてのみ権利が生じます。
児童相談所を通じて養育環境の安定を目的とするケースが多く、普通養子と違い、相続権も「養親の家」に一本化されます。
この点を知らずに遺言を作ると、予期せぬ相続分配になることもあります。
遺言書を用意する理由|相続トラブルを防ぐために
法律上は平等でも、養子と実子が混在する家庭では気持ちの行き違いが生じやすいものです。
「ずっと一緒に暮らしてきたけれど、実子に比べると本当は分け方を調整したい」
「兄弟姉妹でお互いに遠慮があって本音を言えない」
「特定の子どもに感謝を伝えたいが、誤解されたくない」
遺言書を用意することで、こうした想いをきちんと整理し、法的効力を持たせることができます。
遺言書に書くべき具体的な内容
遺言書を作成する際、養子縁組のある家庭では以下の内容を明確にすることが重要です。
1. 財産の分配割合を具体的に記載する
単に「子どもたちに均等に分ける」ではなく、
「長男◯◯に自宅を遺贈、残余財産を3人の子に均等分割する」といった書き方が望ましいです。
特に、不動産を相続させる場合は評価額の差が不公平感を生むため、他の財産とのバランスも考えましょう。
2. 特別養子の場合は相続関係を再確認する
「特別養子だから実親との相続はない」ということを誤解されることがあります。
説明を付言事項に記載すると、残された家族の混乱を減らせます。
3. 付言事項で気持ちを伝える
法的効力はありませんが、分配理由や感謝の言葉を残すことで誤解を防ぎやすくなります。
例:
「◯◯には、これまで私の療養を支えてもらったことに深く感謝しています。
相続分を多くするのは、その感謝の気持ちを形にするためです。」
よくある質問(Q&A)
Q. 養子に遺すとき、実子が遺留分を請求することはありますか?
A. はい、養子も実子も法定相続人なので、遺留分(最低限の取り分)はあります。遺留分を侵害すると請求を受ける可能性があります。
Q. 養子の人数で分割割合は変わりますか?
A. 相続人の人数によって法定相続分は変わりますが、遺言書で自由に調整が可能です。
Q. 特別養子の場合、実親の相続権は完全になくなる?
A. はい、特別養子は実親との親子関係も相続権も消滅します。
公正証書遺言で確実に想いを残す
自筆証書遺言はトラブルや紛失のリスクがあります。
公正証書遺言は以下のメリットがあり、特に養子縁組が絡む家庭におすすめです。
-
法的効力が強く、無効リスクが低い
-
公証役場で保管されるため紛失しない
-
専門家の確認を経て内容が整理される
Kanade行政書士事務所では、公証役場との手続きも丁寧にサポートいたします。
まとめ|養子がいるご家庭こそ遺言書で安心を
養子縁組をしているご家庭では、実子と養子の立場が混在するため、相続で感情的な問題が起こりやすいものです。
遺言書は、その不安を解消する最も有効な手段です。
どの子どもにも気持ちよく引き継いでもらうために、できるだけ早めに準備を進めていきましょう。
ご相談ください
Kanade行政書士事務所では、養子縁組・実子を含む複雑な家族構成の遺言書作成を多数お手伝いしています。
ご家族に安心を残すため、まずはお気軽にご相談ください。