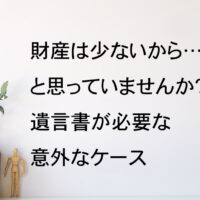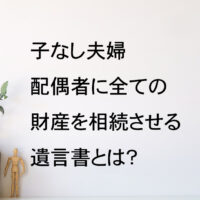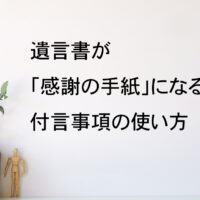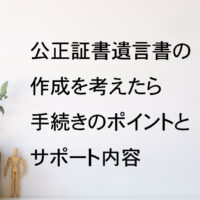コラム
5.102025
遺言書が無効になるケースとは?書いたつもりが意味をなさない「よくある落とし穴」
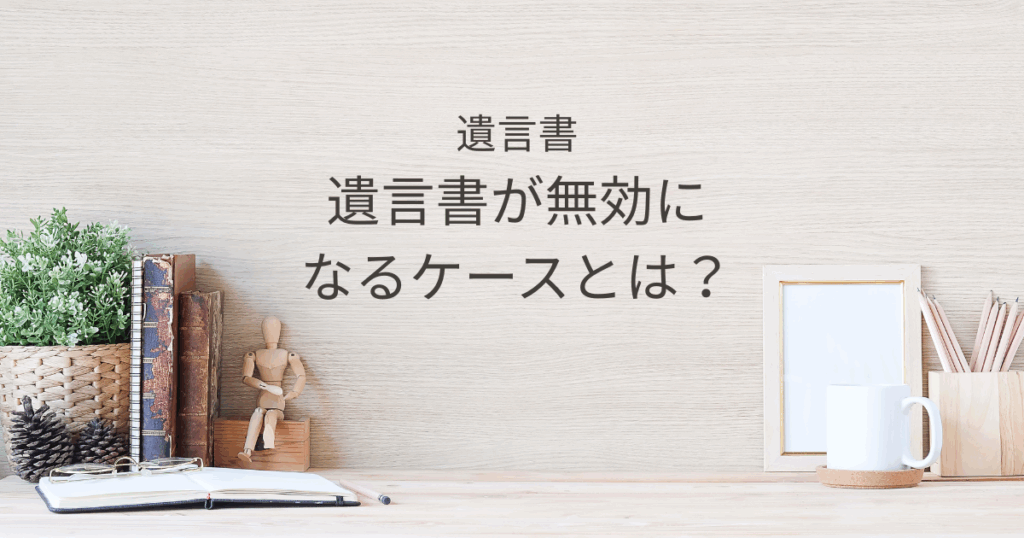
せっかく遺言書を書いても、「形式が整っていなかった」「内容が不明確だった」といった理由で、遺言が無効になるケースは少なくありません。ご本人は“伝えたつもり”でも、残された家族にとってはトラブルの原因になることも。
この記事では、実際にあった無効事例をもとに、どんな点に注意すべきか、どのように備えておけばよいかを解説します。
【どんなときに遺言書は無効になる?】
遺言書が無効と判断される主なパターンは次のとおりです。
■ 自筆証書遺言の形式不備
- 全文自筆で書かれていない(一部がパソコンなど)
- 日付がない、または「令和○年○月吉日」など曖昧
- 押印がない、署名が不完全
■ 内容が不明確・不完全
- 「財産の一部を長男に」など財産の範囲が不明確
- 「次男に感謝を込めて」など受取人の記載が不十分
- 遺言執行者が曖昧、または指定されていない
■ 遺言能力に疑義がある
- 認知症が進行していた時期に作成された
- 医師の診断書などで判断能力がなかったと主張される
■ 証人の欠格・手続き違反(公正証書遺言)
- 証人が相続人やその配偶者だった
- 公証人が形式通りに手続きを行っていなかった
【実例から見る無効パターン】
● 事例1:財産目録だけがパソコン打ちだった自筆証書遺言 → 2020年の法改正前に作成されたもので、全体が自筆でないとして無効に。
● 事例2:本人が認知症と診断された後に作成された遺言 → 記憶障害があったことが主張され、家庭裁判所で効力が争われる結果に。
● 事例3:自宅で作った自筆証書遺言。日付の記載がない遺言書→正式な遺言書に該当せず無効に。
【無効にならないためにできる備え】
- 正しい形式を守る(特に自筆証書遺言の場合)
- 財産や相続人を明確に記載する(口座番号や不動産の詳細など)
- 疑義が生じやすい場合は、医師の診断書などを残しておく
- 公正証書遺言を選択し、専門家のチェックを受ける
- 証人を頼むときは、欠格事由に当てはまらない第三者を
【行政書士ができるサポート】
- 自筆証書遺言の案分チェックと形式要件の確認
- 財産目録の整備・相続関係の図解支援
- 証人サポート(必要に応じて)
- 公証役場とのやり取りを含む、公正証書遺言作成の段取り
※相続に関する登記や相続税に関する内容は司法書士・税理士との連携が必要です。
【まとめ】
遺言書は、「気持ちが伝わればいい」だけではなく、「法的に有効であること」が重要です。 無効になってしまえば、ご本人の思いが届かないばかりか、かえって家族間のトラブルの原因にもなります。
形式の確認や文章の明確化を含め、専門家のサポートを受けて、確実に残す方法を選びましょう。
▶関連記事